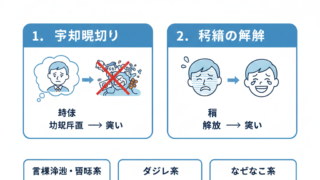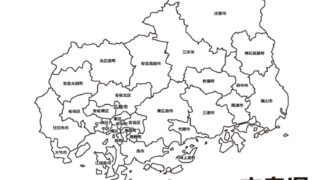【こどもの日】鯉のぼりに込められた願いとは?由来や意味を徹底解説!
こんにちは、皆さん!もうすぐこどもの日ですね。こどもの日といえば、青空を優雅に泳ぐ鯉のぼりを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
ところで、鯉のぼりにはどんな意味や由来があるかご存知ですか?今回は、鯉のぼりに込められた願いや、その歴史についてご紹介します!
鯉のぼりの由来は中国の故事「登竜門」

鯉のぼりの由来は、中国の故事「登竜門」にあります。
- 中国の黄河には「竜門」と呼ばれる激しい滝があり、多くの鯉がその滝を登ろうと試みました。
- しかし、滝を登りきることができた鯉はごくわずかで、その鯉は龍になったという伝説があります。
- この伝説から、「登竜門」は立身出世の関門を意味する言葉となりました。
この伝説が日本に伝わり、「鯉=立身出世の象徴」と考えられるようになったのです。
江戸時代の武家と庶民の風習が合わさって生まれた鯉のぼり
武家の風習
- 端午の節句の重要性:
- 江戸時代初期、端午の節句は武家にとって重要な式日となり、男の子の誕生と成長を祝う行事として盛んになりました。
- 特に、将軍家に男の子が生まれると、幟(のぼり)や旗指物(はたさしもの)を立てて盛大に祝いました。
- 幟や吹き流し:
- 武家では、男の子の誕生を祝い、その成長を願って、家紋の入った幟や吹き流しを飾る習慣がありました。
- これらの飾りは、男の子の立身出世や武運長久を祈願するものでした。
- 五色の吹流しは、武家で生まれました。
- 尚武の精神:
- 端午の節句は、「菖蒲(しょうぶ)の節句」とも呼ばれ、武家では菖蒲を「尚武(しょうぶ)」と結びつけ、武士の精神を重んじる意味合いがありました。
庶民の風習
- 鯉のぼりの誕生:
- 江戸時代中期になると、庶民の間で鯉のぼりを飾る風習が広まりました。
- これは、中国の故事「登竜門」にちなみ、鯉が滝を登って龍になる姿を男の子の立身出世に重ね合わせたものです。
- 武家への対抗心:
- 経済的に豊かになった庶民は、武家に対抗して、豪華な武具の模造品や鯉のぼりを飾るようになりました。
- 鯉のぼりは、庶民が自由に飾れる、男の子の成長を願う象徴として定着しました。
- 庶民文化の発展:
- 江戸時代に入ると、庶民文化が著しく発展し、端午の節句も庶民の間で重要な行事となりました。
- 浮世絵には、庶民が鯉のぼりを飾って楽しむ様子が描かれています。
武家と庶民の融合
- 武家の幟や吹き流しの風習と、庶民の鯉のぼりの風習が融合し、現在の鯉のぼりの形になったと考えられています。
- 時代とともに、鯉のぼりは男の子の成長を願う象徴として、全国的に広まっていきました。
鯉のぼりに込められた3つの意味
では、鯉のぼりには具体的にどんな意味が込められているのでしょうか?
- 子供の健やかな成長と立身出世の願い
- 鯉は生命力が強く、どんな環境でも生きていけることから、子供の健康と長寿を願う意味が込められています。
- また、中国の故事「登竜門」にちなんで、子供が将来困難を乗り越え、立派な人になるようにという願いも込められています。
- 家の繁栄と無病息災の願い
- 鯉のぼりは、子供だけでなく、家族全体の繁栄や無病息災を願う意味も持っています。
- 鯉が空を泳ぐ姿は、家の繁栄を象徴し、家族みんなが健康で幸せに過ごせるようにという願いが込められています。
- 魔除けの意味
- 鯉のぼりの吹き流しに使われる五色は、中国の陰陽五行説に由来しています。
- 五色は、それぞれ木、火、土、金、水を意味し、これらの要素が子供を邪気や災いから守ってくれるという魔除けの意味が込められています。
鯉のぼりの構成とそれぞれの意味
- 真鯉(まごい):黒色で、父親を象徴します。
- 緋鯉(ひごい):赤色またはピンク色で、母親を象徴します。
- 子鯉(こごい):青色、緑色、黄色などで、子供たちを象徴します。
- 吹き流し:五色のものが一般的で、魔除けの意味を持ちます。
これらの色が合わさることで、鯉のぼりには家族の幸せを願う、様々な意味が込められているんですね。

鯉のぼりには子供の成長と家族の幸せを願う意味が込められていた!
今回は、鯉のぼりの由来と意味についてご紹介しました。
鯉のぼりには、子供の健やかな成長や立身出世だけでなく、家族の繁栄や無病息災を願う意味も込められています。
こどもの日には、ぜひ鯉のぼりを飾って、お子さんの成長と家族の幸せを願ってみてはいかがでしょうか?