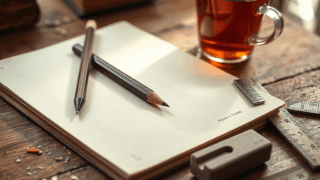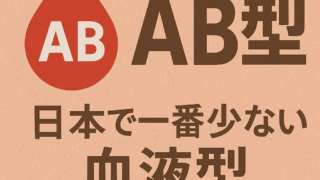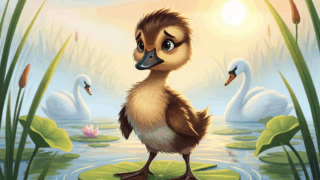球児たちの熱闘!甲子園の知られざる豆知識集⚾️✨
皆さん、こんにちは!野球シーズン真っ盛り、特に高校野球の聖地・甲子園は、球児たちの熱いプレーとスタンドの応援で連日盛り上がっていますよね!📣
今回は、そんな甲子園に関する「へぇ~!」と思えるような、ちょっと意外な豆知識をブログ形式でご紹介したいと思います!これを読めば、甲子園観戦がもっと楽しくなること間違いなしですよ!
- 球場の名前の由来: 「甲子園」という名前は、球場が完成した1924年が干支の「甲子(きのえね)」の年にあたることが由来です。60年に一度の縁起の良い年だったため、この名が付けられました。
- 土の色: 甲子園の土は黒土とされていますが、実は複数の場所の土がブレンドされています。ボールが見やすいように、色合いや粘土質が調整されています。
- ツタの歴史: 甲子園の壁を覆うツタは、球場が完成した1924年の冬に植えられました。当初はコンクリートの殺風景な壁面を飾る目的でしたが、今では甲子園のシンボルの一つとなっています。
- 銀傘の秘密: 内野席を覆う大きな屋根「銀傘」には、雨水を貯蔵する機能があります。貯められた雨水は、グラウンドの散水やトイレの洗浄水として再利用されています。
- 幻の「ヒマラヤスタンド」: 現在のアルプススタンドができた後、外野スタンドが増設された際に、その形状から「ヒマラヤスタンド」という愛称が付けられたことがありましたが、定着しませんでした。
- スコアボードの進化: 初代のスコアボードは手書き式で、延長25回に及ぶ試合で書ききれなくなり、板を継ぎ足したというエピソードがあります。
- 甲子園の土を持ち帰る文化: 敗れた高校球児が甲子園の土を持ち帰るようになったのは、1958年の夏の大会で沖縄代表の首里高校の選手たちが持ち帰ろうとしたのがきっかけと言われています。当時はアメリカ領だった沖縄への持ち込みが検疫で禁止されたため、代わりに球場の小石が贈られました。
- グラウンド整備の秘話: かつて雨上がりで水たまりができたグラウンドを整備する際に、ガソリンを撒いて火をつけ、水分を蒸発させるという大胆な方法がとられたことがありました。