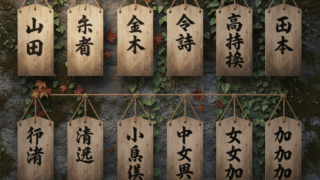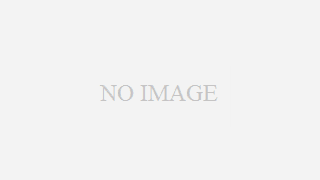鬼火(おにび)とは、日本各地に伝わる怪火の一種で、夜間に空中を漂う正体不明の火の玉のことです。青白い光を放ち、雨の降る夜や湿地、墓地などで目撃されることが多いとされています。

伝承上の解釈
古くから、鬼火は以下のようなものだと考えられてきました。
- 死者の霊や怨念: 人間や動物の死体から生じた霊、あるいは強い恨みや悲しみを抱いて亡くなった人の魂が火となって現れたもの。
- 動物の化身: 特にキツネが口に骨を咥えて火を灯しているように見えることから、「狐火(きつねび)」と呼ばれることもあり、動物が姿を変えたものと考えられました。
科学的な解釈
現代の科学では、鬼火の正体は自然現象によるものと考えられています。有力な説としては、以下のものがあります。
- リン化合物やメタンガスの自然発火: 土葬された遺体などから発生するリン化水素やメタンなどの可燃性ガスが、空気中で自然に発火する現象。特に湿地帯では有機物が分解されやすく、これらのガスが発生しやすいため、鬼火が目撃されやすいと考えられています。
- プラズマ放電: 大気中の電気的な異常によって発生するプラズマが発光する現象。
- 光の屈折: 川原などで光が屈折して、実際とは異なる場所に光が見える現象。
世界各地の類似現象
日本だけでなく、世界各地にも鬼火に似た現象が伝えられています。「ウィルオウィスプ」や「ジャックオーランタン」などがその例で、これらも多くの場合、死者の魂や妖精の仕業とされてきました。
まとめ
鬼火は、古くから人々の間で様々な解釈がされてきた不思議な現象です。現代科学では自然現象として説明されることが多いですが、その神秘的なイメージは今もなお多くの人々の興味を惹きつけてやみません。