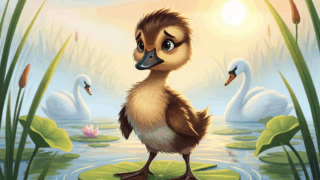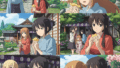スポンサーリンク
フードロス削減への取り組み:家庭でできること、社会で進むこと
フードロスとは?
「フードロス」とは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。これは、生産・加工・流通の段階で発生するものと、私たち消費者の家庭から出るものの2種類に大きく分けられます。世界中で年間、莫大な量の食料が捨てられており、これは環境負荷の増大や経済的損失に繋がっています。
家庭でできるフードロス削減の取り組み
私たちは日々の生活の中で、意識するだけでフードロスを大きく減らすことができます。
1. 買い物前に計画を立てる
- 冷蔵庫の中身を確認する: 買う前に、今ある食材を把握しましょう。同じものを買ってしまったり、奥に眠っている食材を見つけたりできます。
- 献立をざっくり決める: 献立を決めてから買い物リストを作ると、必要なものだけを無駄なく買えます。週末にまとめて決めるのもおすすめです。
- 買い物リストを作る: リストがあれば、特売品に釣られて不要なものまで買うのを防げます。
2. 食材を上手に保存する
食材が長持ちすれば、使い切るチャンスが増えます。
- 野菜の保存方法を知る: 例えば、葉物野菜は湿らせた新聞紙に包んで冷蔵庫に入れると長持ちします。根菜類は冷暗所で保存するなど、野菜の種類によって適した方法があります。
- 肉・魚は「小分け冷凍」: 大容量で買ったお肉やお魚は、すぐに使う分以外は小分けにして冷凍しておきましょう。使うときに必要な分だけ解凍できるので便利です。
- 「冷凍できるもの」を知る: パン、ご飯、キノコ類、使いかけの薬味(ねぎ、しょうがなど)なども冷凍できます。いざという時に役立ちます。
3. 食材を使い切る工夫をする
- 「使い切りレシピ」を活用する: 残り野菜や使いかけの食材を使ったレシピを探してみましょう。インターネット上には多くのアイデアがあります。
- 「MEAL PREP(ミールプレップ)」に挑戦する: 週末にまとめて食材の下ごしらえや調理をしておくことで、平日の食事準備が楽になるだけでなく、食材を計画的に使い切ることができます。
- 「食べる直前に使い切る」を意識する: 賞味期限や消費期限が近いものから優先的に使うように心がけましょう。
4. 残り物を美味しく活用する
もし残ってしまっても大丈夫!
- 賞味期限・消費期限を意識する: 期限が近いものから先に食べるようにしましょう。
- 食べ残しは翌日のお楽しみに: 余ったおかずは、翌日のお弁当に入れたり、リメイクして別の料理に変身させたりできます。カレーをドリアにしたり、シチューをグラタンにしたりなど。
- 少しだけ残すなら捨てる前に考える: 本当に食べられないか、誰か他の家族が食べるか、など一度立ち止まって考えましょう。
社会で進むフードロス削減の取り組み
個人だけでなく、社会全体でもフードロス削減に向けた様々な取り組みが進められています。
1. 食品リサイクル
食べ残しや規格外の食品などを家畜の飼料や肥料、バイオガスなどにリサイクルする動きが広まっています。これにより、廃棄物を減らすだけでなく、新たな資源として活用することができます。
2. フードバンク・フードドライブ
- フードバンク: まだ食べられるのに様々な理由で市場に出回らない食品を企業や個人から寄付してもらい、生活困窮者支援団体などに提供する活動です。
- フードドライブ: 家庭で余っている食品を持ち寄り、フードバンクを通じて必要な人に届ける活動です。地域のイベントや学校などで開催されることがあります。
3. テクノロジーを活用した取り組み
AIを活用して需要予測を行い、食品の過剰生産を抑制したり、余剰食品をマッチングアプリで販売したりするサービスも登場しています。
まとめ
フードロス削減は、私たちの食卓から地球の未来まで、あらゆる側面に良い影響を与える大切な取り組みです。小さな一歩でも、多くの人が実践することで大きな変化に繋がります。今日からできることを始めてみませんか?