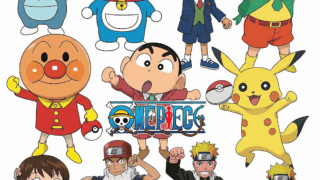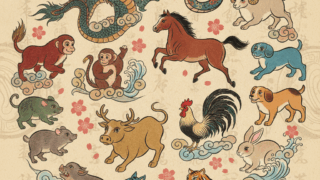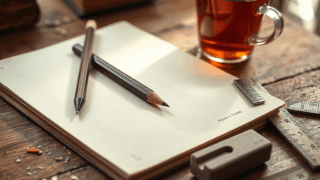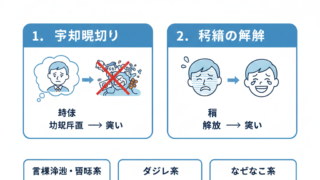超音波診断装置は、超音波を体の内部に当て、その反射波を利用して臓器や組織の様子を画像化する医療機器です。エコー、超音波エコー、あるいは単にエコー検査とも呼ばれます。
仕組み
超音波診断装置は、主に以下の3つの部分で構成されています。
- プローブ(探触子): 超音波を発生させ、体内の組織から跳ね返ってきた超音波(反射波)を受信する役割を担います。
- 本体(スキャナー): プローブが受信した反射波を電気信号に変換し、画像処理を行います。
- モニター: 処理された画像をリアルタイムで表示します。
プローブから発せられた超音波は、体内の臓器や組織に当たって反射します。この反射波をプローブが再び受け取り、その反射時間や強さをコンピューターが解析することで、体内の様子を画像としてリアルタイムで表示します。この技術は、音の反射を利用して距離を測定するコウモリの「エコーロケーション」と同じ原理です。
特徴と利点
超音波診断装置は、他の画像診断装置と比較して以下のような特徴があります。
- 安全性: X線やCTスキャンのように放射線を使用しないため、被ばくの心配がありません。そのため、妊婦さんや乳幼児、頻繁な検査が必要な患者さんにも安全に使用できます。
- リアルタイム: 臓器の動きや血流をリアルタイムで観察できます。心臓の拍動、胎児の動き、腹部臓器の動きなどをその場で確認できるため、動的な診断に優れています。
- 非侵襲性: プローブを体の表面に当てるだけなので、痛みや不快感がほとんどありません。
- 簡便性: 装置が比較的コンパクトで移動可能なものが多く、ベッドサイドや診察室で手軽に検査ができます。
- 高分解能: 臓器や組織の表面だけでなく、内部の微細な構造まで詳細に観察することが可能です。
主な用途
超音波診断装置は、多岐にわたる診療科で活用されています。
-
- 産婦人科: 胎児の発育状況の確認、胎盤の位置、羊水の量などを観察します。
- 循環器内科: 心臓の動き、弁の機能、血流の速さなどを評価し、心臓病の診断に用います。
- 消化器内科: 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓などの腹部臓器の腫瘍や結石、炎症などを調べます。
- 乳腺外科: 乳がんの早期発見のための検査として広く使われています。
- 整形外科: 筋肉や腱、靭帯の損傷の有無を確認します。
- 血管外科: 動脈瘤や静脈血栓の有無を調べます。