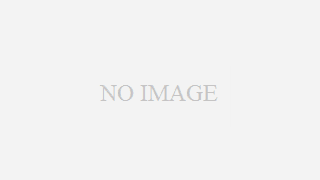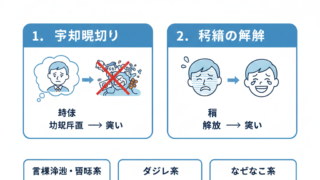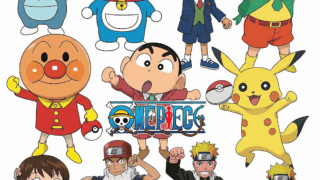リニア新幹線は、超電導磁気浮上方式を利用した次世代の高速鉄道システムです。正式には「リニア中央新幹線」と呼ばれ、JR東海が東京(品川駅)と大阪(新大阪駅)を結ぶ計画を進めています。
走行の仕組み
リニア新幹線の最大の特徴は、車輪を使わず、磁力の力で車体を浮上させて走行する点です。
- 推進:地上に設置された推進コイルと、車両に搭載された強力な超電導磁石が作り出す磁力の反発・吸引を利用して、車体を前進させます。
- 浮上:時速150km程度になると、車両の超電導磁石が地上のコイルを通過する際に電磁誘導が発生し、車体が約10cm浮き上がります。これにより、車輪とレールの摩擦がなくなり、空気抵抗のみで超高速走行が可能になります。
- 案内:浮上と同じコイルが、車両が左右にずれると磁力で引き戻す働きも担っており、自動的に線路の中央を走行するよう制御されます。
この技術により、最高時速505kmでの営業運転が計画されています。
計画の現状
リニア中央新幹線は、以下の2段階で建設が予定されていますが、現在は工事の遅延により、当初の開業目標は困難とされています。
- 品川・名古屋間
- 当初の開業目標:2027年
- 所要時間:約40分(現在の東海道新幹線は約1時間40分)
- 現状:静岡県内の南アルプストンネル工事をめぐり、環境への影響(水資源など)について協議が続いており、開業時期は未定となっています。
- 名古屋・大阪間
- 開業目標:2045年
メリットと課題
メリット
- 移動時間の短縮: 東京・名古屋・大阪間の移動時間が大幅に短縮され、人々の交流やビジネスの効率化が期待されます。
- 国土強靭化: 東海道新幹線が災害で不通になった際の代替路線となり、首都圏と関西圏を結ぶ交通網を確保できます。
- 新たな経済圏の創出: 三大都市圏が一体となった巨大な経済圏「スーパー・メガリージョン」を形成し、国際競争力の強化に貢献すると期待されています。
課題
- 環境への影響: 南アルプスを貫く長大トンネル工事による、水資源や自然環境への影響が大きな懸念となっています。
- 巨額な建設費: 総事業費は約9兆円に上る巨大なプロジェクトであり、その費用負担が課題です。
- ストロー現象: 地方都市から大都市へ、人口や産業が流出する「ストロー現象」の発生が懸念されています。