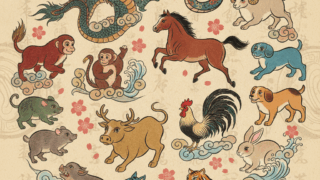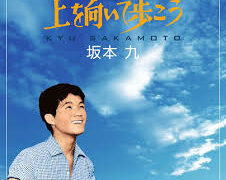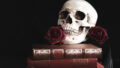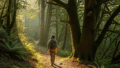たばこの歴史は、新大陸(アメリカ大陸)で生まれ、世界中に広がり、社会や経済、文化に大きな影響を与えてきました。その歴史をいくつかの時代に分けて詳しくご紹介します。
1. 起源と新大陸での利用(紀元前〜15世紀)
たばこは、もともと南米のアンデス山脈付近が原産とされるナス科の植物です。紀元前から栽培され、特にマヤ文明やアステカ文明といったメソアメリカの文明では、儀式や呪術、医療、宗教的な目的で使われていました。
- 儀式・宗教: 神への供物として用いられたり、予言や占いの際にたばこの煙が使われたりしました。
- 薬用: 鎮痛剤や消毒薬として使われることもありました。
この時代、たばこは単なる嗜好品ではなく、特別な力を持つ神聖な植物として扱われていました。
2. ヨーロッパへの伝播(15世紀末〜16世紀)
1492年にクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到達した際、先住民がたばこを吸っているのを目撃し、ヨーロッパに持ち帰ったのが始まりとされています。
- 伝播のきっかけ: コロンブス一行は、キューバの先住民から乾燥したたばこの葉を贈られました。当初は珍しい植物として扱われましたが、やがてその効用や嗜好性が注目されるようになります。
- ヨーロッパでの広まり: 16世紀に入ると、たばこはフランスやスペインの宮廷で、薬用植物として珍重されるようになりました。特に、フランスのジャン・ニコスキーはたばこの薬効を称賛し、これが「ニコチン」という名の由来になったとも言われています。
3. 日本への伝来と普及(16世紀後半〜江戸時代)
日本にたばこが伝わった正確な時期は諸説ありますが、一般的には16世紀後半、安土桃山時代にポルトガル人によって鉄砲とともに持ち込まれたとされています。
- 伝来: 慶長年間(1596-1615年)にはすでに日本で栽培が始まり、庶民の間でも喫煙習慣が広まりました。
- 江戸時代の喫煙文化: 江戸時代には、たばこは広く庶民に浸透し、キセル(煙管)が喫煙具として定着しました。浮世絵にも、たばこを吸う女性の姿が描かれるなど、文化の一部として根付いていきました。しかし、火災の原因になることや、奢侈(しゃし)であるという理由から、幕府による禁令がたびたび出されました。
4. 産業としての発展と国家財政への影響(明治時代〜昭和時代)
明治時代に入ると、たばこは国家の重要な財源となります。
- 専売制度の開始: 日清戦争や日露戦争といった戦費調達のため、日本政府はたばこに注目しました。1898年(明治31年)に「葉煙草専売法」を制定し、たばこの製造と販売を国が独占する専売制度を開始します。
- 日本専売公社の設立: 1949年(昭和24年)には「日本専売公社」が設立され、たばこ、塩、樟脳の製造・販売を独占的に行いました。
- 紙巻きたばこの普及: 欧米から伝わった紙巻きたばこが、明治以降に庶民に広く普及し、キセルから紙巻きたばこへと喫煙スタイルが変化していきました。
- 喫煙率のピーク: 戦後、専売公社が喫煙を奨励したこともあり、昭和40年頃には成人男性の喫煙率が80%を超えるほどになりました。
5. 規制と健康意識の高まり(昭和末期〜現代)
たばこの健康被害が広く認識されるようになり、世界的に規制の動きが強まります。
- 科学的根拠の確立: 1960年代には、たばこと肺がんの関係を示す科学的な研究が発表され、世界的にたばこの健康被害への意識が高まりました。
- 日本たばこ産業株式会社(JT)の設立: 1985年(昭和60年)、国際化の進展と国の財政再建を背景に、日本専売公社は民営化され、「日本たばこ産業株式会社(JT)」が設立されました。これにより、日本のたばこ市場は海外メーカーにも開放されました。
- 禁煙・分煙の広まり: 1980年代以降、公共の場での分煙化が進み、「嫌煙権」という言葉も生まれました。
- 法整備と規制強化: 2000年代に入ると、未成年者喫煙禁止法、健康増進法、受動喫煙防止条例などが施行され、喫煙場所の制限やたばこ税の引き上げなど、より厳しい規制が導入されました。
- 加熱式たばこの登場: 近年では、従来の紙巻きたばこに代わり、煙が出ない「加熱式たばこ」が登場し、喫煙者の選択肢の一つとなっています。
たばこは、単なる植物から、儀式に使われる神聖なもの、そして国家財政を支える商品へとその役割を変え、現代では健康問題と環境問題の観点から厳しい規制下に置かれるようになりました。その歴史は、人類の文化、社会、そして経済の変遷を映し出す鏡とも言えます。