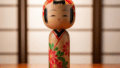萩焼の魅力に迫る!「七化け」を愉しむ、素朴で奥深い器の世界
日本の伝統工芸品の中でも、特に茶道の世界で珍重されてきた萩焼。山口県萩市で生まれたこの陶器は、素朴で温かみのある風合いが特徴です。しかし、その最大の魅力は、使い込むほどに表情を変える「七化け(ななばけ)」と呼ばれる変化にあります。この記事では、萩焼の歴史からその製法、そして日常での楽しみ方まで、萩焼の奥深い世界をたっぷりご紹介します。
萩焼の歴史と特徴:400年以上の時を刻む美
萩焼の歴史は、今から約400年以上前に遡ります。豊臣秀吉の文禄・慶長の役(朝鮮出兵)の際、毛利輝元が朝鮮から陶工である李勺光(りしゃっこう)と李敬(りけい)を連れ帰り、萩の地で開窯させたのが始まりとされています。彼らの故郷の陶法を元に、日本の美意識と融合して独自の発展を遂げました。
萩焼は、他の焼き物とは一線を画すいくつかの特徴を持っています。
- 素朴な土の風合い: 萩焼の原料となる土は、粒子の粗い大道土(だいどうつち)や見島土(みしまつち)などを使います。そのため、焼成後も土の粒子が残り、柔らかな手触りと素朴な風合いが生まれます。
- 貫入(かんにゅう): 釉薬の収縮率の違いによってできる、表面の細かいヒビのことです。このヒビは使い込むほどに茶渋や油分が染み込み、景色を変えていきます。
- 高台の切り込み: 萩焼の茶碗の裏には、高台(こうだい)と呼ばれる底の部分に切り込みが入っていることがあります。これは「見込み(みこみ)」と呼ばれ、窯の中で器を並べる際に高台がくっつかないようにするための工夫です。
「七化け」を愉しむ、萩焼の真髄
萩焼の最大の魅力であり、多くの人を惹きつける理由が、使い込むほどに色合いや風合いが変化する「七化け」です。
萩焼は、その土の性質上、吸水性が非常に高いため、使い始めは淡く柔らかな色合いをしています。しかし、お茶やコーヒー、お酒などを注いで使い続けると、水分が釉薬の貫入からゆっくりと内部に染み込んでいきます。その結果、器の色がだんだんと深く、そして艶やかな色合いへと変化していくのです。
この「七化け」の過程は、器を「育てる」と言い換えることができます。使う人の生活や使い方によって、器は世界に一つしかない独自の表情を宿していきます。この変化を愉しむことが、萩焼の醍醐味なのです。
日常で萩焼を愉しむための使い方
「七化け」を存分に楽しむためには、普段から積極的に萩焼を生活に取り入れることが大切です。
- まずは日常の器から: 湯呑みやマグカップ、小皿など、毎日使うものから萩焼を取り入れてみましょう。特に、コーヒーや紅茶、緑茶など色の濃い飲み物を飲むと、七化けの変化をより早く実感できます。
- 正しい使い方でお手入れ: 萩焼は吸水性が高いため、使う前には水に浸してから使うのがおすすめです。こうすることで、シミや匂いがつきにくくなります。使い終わった後は、なるべく早く洗い、しっかり乾燥させましょう。
- 料理との相性: 萩焼の素朴な色合いは、和食との相性が抜群です。煮物や和え物を盛り付けると、料理の色を一層引き立ててくれます。また、ビールを注ぐと、きめ細かな泡立ちになり、口当たりがまろやかになるとも言われています。
萩焼の「景色」を知る
窯の中で生まれる一つ一つの模様や風合いは「景色」と呼ばれ、萩焼の個性を決定づけます。
- 萩釉(はぎゆう): 萩焼の代表的な釉薬で、柔らかな白やベージュ色が特徴です。
- 青萩(あおはぎ): 釉薬の成分や焼成時の窯の温度によって、淡い青色に発色する景色です。
- 見島土(みしまつち): 萩の沖合にある見島で採れる土で、焼き上がりが深みのある赤褐色になります。
これらの「景色」は、同じ窯で焼かれた器でも一つとして同じものはありません。器を選ぶ際には、自分の好みの景色を探してみるのも楽しみの一つです。
どこで萩焼に出会える?
萩市には、萩焼の窯元やギャラリーが数多く点在しています。実際に足を運んで、手に取って、作家さんと話をしながら器を選ぶのは、とても贅沢な時間です。萩焼まつりなどのイベントに参加すれば、普段見られないような作品に出会えるかもしれません。
もちろん、百貨店やオンラインショップでも購入できます。初めて萩焼を買う場合は、まずは自分の「直感」を信じて、使ってみたいと思う器を選んでみるのが良いでしょう。
萩焼は、決して華やかな器ではありません。しかし、使う人の手によって育っていくその姿は、まるで人生のようにも思えます。ぜひあなたも、萩焼と共に、日々の暮らしに豊かな彩りを与えてみませんか。