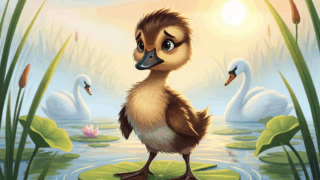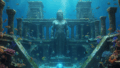中国地方(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県)は、瀬戸内海と日本海に面し、豊かな海の幸と、山間部の素朴な恵みを活かした多様な郷土料理が特徴です。
地域ごとに代表的な郷土料理をご紹介します。
🐟 広島県:海の幸の王者と粉もん文化
瀬戸内海の豊かな恵みと、独自の食文化が発達した地域です。
牡蠣の土手鍋(かきのどてなべ)
広島が誇るカキを使った鍋料理。鍋のふちに味噌を塗りつけ、カキや野菜を煮ながら、味噌を少しずつ溶いて味を調整していくのが特徴です。「土手」のように味噌を盛ることからこの名がつきました。

あなご飯(あなごめし)
宮島(厳島)が発祥とされる駅弁としても有名な郷土料理。穴子の骨で取った出汁で炊いたご飯の上に、甘辛いタレで蒲焼きにした瀬戸内のあなごを乗せて味わいます。

広島風お好み焼き
小麦粉の生地を薄く引き、その上にキャベツ、豚肉、卵、そして中華麺(そば)またはうどんを重ねて焼くのが特徴です。生地と具材を混ぜない「重ね焼き」スタイルで、ボリュームと食感が楽しめます。

🍑 岡山県:祭り寿司と出世魚
瀬戸内側の温暖な気候と、備前・備中・美作の文化が反映された料理が多いです。
ばら寿司(祭り寿司)
「備前ばら寿司」とも呼ばれる、岡山を代表する豪華なちらし寿司です。江戸時代、倹約令が出た際に「一汁一菜」に見せるため、皿の底に具材を隠したのが始まりという説があります。エビ、アナゴ、タコなどの海の幸や、季節の山の幸をふんだんに盛り付けます。

ままかり寿司
サッパという小魚を塩漬けや酢漬けにした「ままかり」を使ったお寿司。あまりの美味しさに隣の家にご飯(まま)を借りに(かり)行くほど箸が止まらなくなる、というのが名前の由来です。

ぶり雑煮
岡山県の南部(特に海側)でお正月に食べられる雑煮。ブリは成長と共に名前が変わる出世魚であることから、縁起物として使われます。

🐡 山口県:ふぐと独特の瓦文化
三方を海に囲まれ、特に日本有数のフグ(河豚)の水揚げ地として知られます。
ふぐ料理(ふぐ刺し、ふぐちり)
山口県ではフグを「福」に通じる**「ふく」**と呼びます。特に下関市(旧・馬関)はフグ食文化の中心地です。薄く引いた刺身(てっさ)や鍋(てっちり)は、高級料理として知られます。

瓦そば(かわらそば)
熱した**瓦(かわら)**の上に、茶そばと錦糸卵、甘辛く煮た牛肉などを乗せて、温かいめんつゆでいただく料理です。瓦の熱でそばがパリパリにおこげになる独特の食感が人気です。

大平(おおひら)
山口県の中央部から西部にかけて、お祝いの席で出される煮物です。大きな平たい器(大平)に、鶏肉、里芋、椎茸などの山の幸と、エビや練り物などの海の幸を盛り合わせて煮込みます。

🦀 島根県:神話の国の素朴な味覚
日本海に面し、神話の舞台としても知られる土地の、素朴で歴史ある料理が特徴です。
出雲そば
出雲地方のそばは、そばの実を皮ごと挽く**「挽きぐるみ」という製法で作られるため、色が濃く、香りが高く、コシが強いのが特徴です。一般的な食べ方として、円形の漆器に盛り付ける「割子(わりご)そば」**があります。

しじみ汁
日本海とつながる汽水湖である**宍道湖(しんじこ)**で獲れるヤマトシジミを使った汁物。宍道湖のシジミは粒が大きく、濃厚な旨味があり、島の食卓に欠かせません。

ぼてぼて茶
松江地方に伝わる独特のお茶の飲み方。泡立てた番茶に、ご飯や漬物、煮物などを入れて、具材と一緒にお茶をすするように食べます。

⛰️ 鳥取県:海山の幸とユニークな鍋
山陰地方に位置し、日本海側の魚介と、大山の恵みがあります。
いただき
鳥取県西部の弓浜(ゆみはま)半島に伝わる郷土料理。油揚げの中に、生米と野菜を詰めて、甘辛いだしでじっくりと煮込みます。農作業の合間に食べる保存食・まかない料理として親しまれてきました。

カニ料理(松葉がに)
冬の味覚の王様、**松葉がに(ズワイガニ)**は鳥取を代表する食材です。刺身、焼きガニ、カニ鍋など、さまざまな調理法で楽しまれます。

とうふちくわ
鳥取県東部で広く食べられている加工品。魚のすり身に豆腐を混ぜて作るため、普通のちくわよりもヘルシーで柔らかい食感が特徴です。

中国地方は、海と山の幸に恵まれた、非常に食文化の豊かな地域です。旅をする際は、ぜひその土地ならではの郷土料理を味わってみてください。