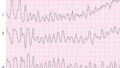初詣に行く期間に厳密な決まりはありませんが、一般的には**「松の内(まつのうち)」**と呼ばれる期間を目安にするのが良いとされています。
「松の内」とは、年神様(としがみさま)を迎えるための門松などの正月飾りを飾っておく期間のことです。
初詣の一般的な期間の目安
| 期間の名称 | 関東地方の目安 | 関西地方の目安 |
| 三が日 | 1月1日〜1月3日 | 1月1日〜1月3日 |
| 松の内 | 1月7日頃まで | 1月15日頃まで |
- 三が日(1月1日〜3日):最も多くの人が参拝に訪れ、混雑する期間です。
- 松の内:この期間内に参拝するのが最も一般的とされています。地域によって期間が異なるため、上記の目安を参考にしてください。
松の内を過ぎた場合
松の内の期間に参拝できなかった場合でも、初詣に行ってはいけないというルールはありません。
- 1月いっぱい:一般的に1月中であれば「初詣」と考える人が多いです。
- 節分まで:遅くとも、旧暦で新年が始まる目安とされる**節分(2月3日頃)**までに参拝すると良い、という考え方もあります。
近年は、混雑を避けるために「三が日」を避けたり、年内から参拝する「幸先詣(さいさきもうで)」を推奨する神社も増えています。ご自身の都合の良いタイミングで、心を込めて参拝しましょう。
神社の正しい参拝手順(初詣の作法)
参拝は、神様の領域である境内に入ることから始まります。それぞれの場所に意味がありますので、作法を守って心を込めてお参りしましょう。
1. 鳥居をくぐる(神域への入口)
- 一礼をする: 鳥居は神域と俗界を区切る境です。鳥居の前で立ち止まり、軽く一礼をしてからくぐります。
- 中央を避ける: 参道の**中央(正中/せいちゅう)**は神様の通り道とされているため、中央を避けて、左右どちらかの端を歩きましょう。
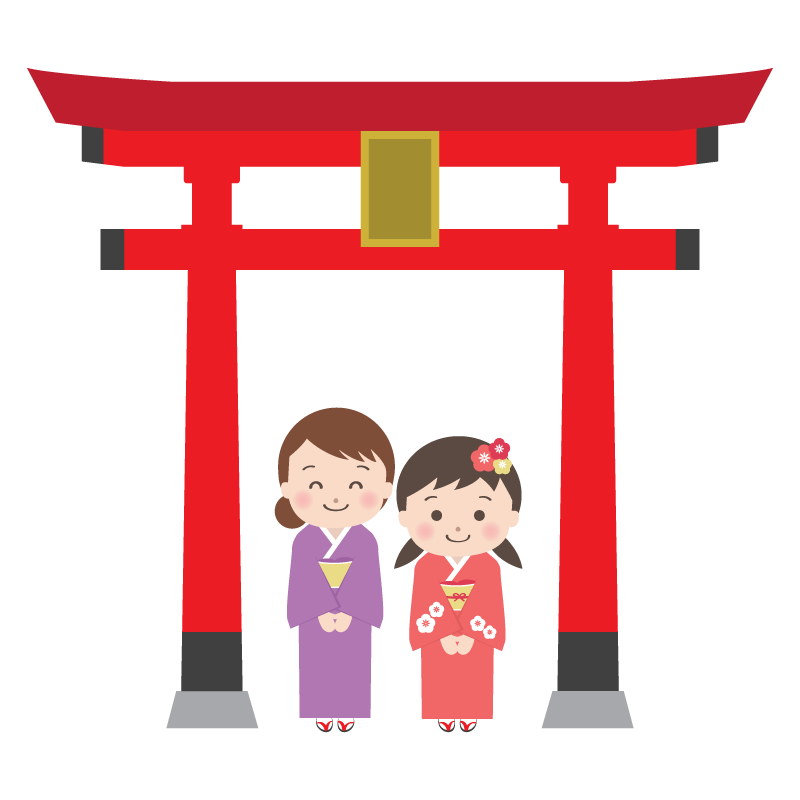
2. 手水舎で心身を清める(手水/てみず)
参拝の前に、手水舎(ちょうずしゃ/てみずや)で手と口を清めます。柄杓(ひしゃく)に汲んだ一杯の水で行うのが基本です。
- 右手に柄杓を持ち、左手を清める。
- 柄杓を左手に持ち替え、右手を清める。
- 再度柄杓を右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぐ(柄杓から直接口をつけない)。
- 左手をもう一度清める。
- 柄杓を立てて、残った水で柄の部分を洗い流し、元の場所に戻す。

3. 拝殿でのお参り(二礼二拍手一礼)
手水で清めた後、拝殿(本殿)に進み、神様にご挨拶をします。
- お賽銭を納める: 賽銭箱に静かに、心を込めてお賽銭を入れます(投げつけない)。
- 鈴を鳴らす: 鈴があれば鳴らします。これは神様を呼び、清める意味があるとされます。
- 二拝(二礼): 姿勢を正し、深くお辞儀(およそ90度)を2回行います。
- 二拍手: 両手を胸の高さで合わせ、右手を少し(指一本分ほど)下にずらします。両手を肩幅程度に開いて、拍手を2回打ちます。
- お祈り: ずらした右手を元に戻し、両手を合わせたまま、神様への感謝を伝えた後に願い事を心の中で唱えます。
- 一拝(一礼): 最後に深くお辞儀を1回行います。

4. 境内を出る時
- 境内から出る際も、鳥居をくぐり終えたら、社殿の方に向き直って軽く一礼をします。

【注意】 お寺の場合は、合掌のみで拍手はしません。神社とお寺で参拝方法が異なりますので注意しましょう。
縁起が良いとされる金額の例
- 5円玉: 「ご縁」があるように
- 15円: 「十分なご縁」があるように
- 25円: 「二重のご縁」があるように
- 115円: 「いいご縁」があるように
- 5円玉と50円玉の組み合わせ: 「穴が開いている」50円玉を加えて「見通しがよい」「運が通る」とされ、より縁起が良いとされます。
縁起が悪いとされる金額の例
- 10円玉: 「遠縁」になるという語呂合わせ
- 500円玉: 「これ以上の効果(硬貨)」がない、という語呂合わせ
- 65円、75円、85円など: 「ろくなご縁がない」「何のご縁もない」といった語呂合わせ。
これは例なのでお賽銭の金額に決まりは無く、自由です。
「ご縁」にちなんだ語呂合わせで金額を決めると、より気持ちを込めることができます。
縁起が良いとされる金額や避けた方が良いとされる金額は、語呂合わせから来ています。
最終的には、感謝の気持ちを込めて、自分が納得できる金額を納めるのが良いでしょう。
まとめ
初詣は、新しい年の幸運を願うための大切な行事です。今回は一般的な初詣の作法を紹介しましたが、行かれる神社によってはルールが存在する為、事前に確認などを行いましょう。
そして気持ちよく新年が迎えられるようにお参りに行きましょう。



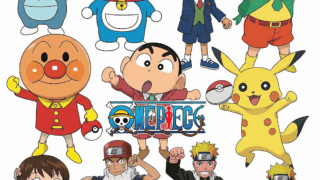

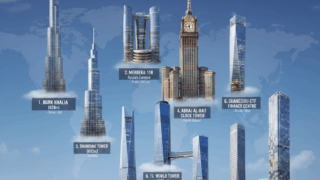








-120x68.jpg)