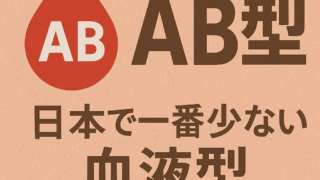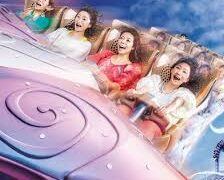餃子の歴史は非常に古く、その起源は中国にあります。時代とともに形や食べ方が変化し、世界中で愛される料理となりました。
1. 餃子の起源:古代中国
餃子の起源は中国とされており、その歴史は数千年前に遡ります。
- 紀元前3000年頃: 古代メソポタミア文明の遺跡から、小麦粉の皮に具を包んだ食べ物が見つかっているという説もあります。これがシルクロードを経て中国に伝わった可能性も指摘されています。
- 漢の時代(紀元前206年~): 小麦粉を使った皮で調理が行われていたことが確認されています。当時の中国北部では、肉や魚、野菜を皮で包み、煮たり茹でたりして食べられていたと考えられています。
- 唐の時代(618年~907年): 敦煌の唐代の墳墓からは、副葬品として壺に入った乾燥した餃子が発見されており、現在の餃子とほぼ同様のものがこの時代に食されていたことが分かっています。
- 名前の由来: 「餃子(ジャオズ)」という名称は、明の時代(1368年~)に誕生したとされています。また、「交子(ジャオズ):子が交わる、子を授かる」という言葉と同じ音であることから、「子宝に恵まれるように」という願いも込められた縁起物として、特に旧正月(春節)に食べられる習慣があります。
2. 日本への伝来と独自の発展
日本に餃子が本格的に普及したのは、比較的最近のことです。
- 江戸時代: 1778年の中国料理書『卓子調烹法』で初めて餃子が紹介されたり、10年ほど後に中国事情を記した書『清俗紀聞』に絵入りで記されたりしましたが、庶民にはあまり普及しませんでした。
- 第二次世界大戦後: 満州(現在の中国東北部)にいた日本兵が現地で餃子を食べ、その味を懐かしんで日本でも作るようになったのが、日本における餃子普及の大きなきっかけとされています。
- 「焼き餃子」の定着: 中国では水餃子や蒸し餃子が主流であり、焼き餃子は残った水餃子を焼き直して食べる「鍋貼(グォティエ)」として認識されていました。しかし、日本では主食であるご飯に合うことや、香ばしい匂いが好まれたことから、薄い皮にニンニクなどを加えた日本独自の「焼き餃子」が主流となりました。一説には、引揚者が茹で餃子を作ろうとしたものの、鍋がなく代わりに鉄板を使ったのが始まりとも言われています。
- 家庭への普及: 1950年代からは餃子の皮が市販されるようになり、1960年には日本初の冷凍餃子が販売されました。1959年にはNHKの「きょうの料理」で餃子の作り方が紹介されるなど、メディアでの露出も増え、家庭料理としても広く定着していきました。
今日では、餃子はラーメンやカレーライスなどと同じように、日本の国民食の一つとして親しまれています。地域によっては「浜松餃子」や「宇都宮餃子」のように独自の発展を遂げ、その多様な味わいが楽しまれています。