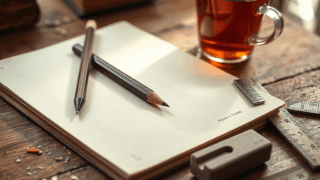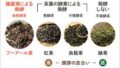微小RNA(microRNA: miRNA)とは?
微小RNAは、長さが約20〜25塩基の非常に小さなRNA分子で、遺伝子発現の調節に重要な役割を果たしています。従来の遺伝子(DNA)から作られるRNA(メッセンジャーRNA)がタンパク質の設計図となるのに対し、微小RNAはタンパク質自体を作ることはありません。しかし、メッセンジャーRNAに結合することで、その働きを抑制したり分解したりして、間接的に遺伝子の発現量をコントロールしています。
微小RNAは、細胞の増殖、分化、アポトーシス(細胞死)など、様々な生命活動に関わっており、その種類や発現量は、病気の状態によって大きく変動することがわかってきました。特に、がん細胞は正常な細胞とは異なる微小RNAを大量に分泌することが知られています。
微小RNA検査の原理
微小RNA検査は、このがん細胞から分泌される特有の微小RNAを「バイオマーカー」として利用します。具体的には、以下のステップで検査が行われます。
- 検体採取: 採血や採尿によって、患者の体液(血液、尿など)を採取します。
- 微小RNAの抽出: 採取した検体から、微小RNAを分離・抽出します。
- 微小RNAの解析: 抽出した微小RNAの種類と量を、専用の解析装置や技術(RNAチップなど)を用いて測定します。
- AIによるデータ解析: 測定された微小RNAのデータを、膨大な量の健康な人のがん患者のデータと比較します。この際、AI(人工知能)が用いられることが多く、複数の微小RNAの組み合わせから、特定のがんのリスクを高い精度で判定するアルゴリズムが構築されています。
- リスク評価: 解析結果に基づき、現在のがんリスク(ステージIなどの早期がんを含む)を評価します。
従来の検査との違いと利点
従来の検査(画像診断、腫瘍マーカーなど)
- 画像診断(CT、MRI、PETなど): がんの「形」や「代謝活動」を画像化して発見するため、ある程度の大きさになってからでないと見つかりにくいという限界があります。
- 腫瘍マーカー: 採血で測定できる手軽な検査ですが、特異性が低く、早期がんの発見には向かないことが多いです。
微小RNA検査
- 超早期発見の可能性: がん細胞がごく初期の段階から分泌する微小RNAの変化を捉えることで、画像診断では見つけられないような小さながんの発見につながる可能性があります。
- 高い簡便性: 採血や採尿だけで検査できるため、患者の身体的な負担が極めて少ないです。
- 複数のがん種を一度に検査: 一度の検体採取で、複数のがん種のリスクを同時に評価できるサービスも存在します。例えば、すい臓がん、胃がん、肺がん、乳がんなど、早期発見が難しいがんのリスクを一度に調べることが可能です。
検査の課題と注意点
- 診断の補助: 微小RNA検査は、あくまで「がんのリスクを評価する」ためのスクリーニング検査です。検査結果でリスクが高いと判定された場合でも、それだけで「がんである」と確定診断されるわけではありません。必ず精密検査(画像診断、生検など)を受けて、最終的な診断をする必要があります。
- 保険適用外: 多くの微小RNA検査は、まだ研究段階であったり、実用化されて間もないため、公的医療保険の適用外である自由診療として提供されています。そのため、費用は全額自己負担となります。
- 施設やサービスによる精度の差: 微小RNA検査の精度は、サービスを提供する企業や研究機関によって異なります。検査を受ける際は、どのようながん種に対応しているか、どのようなデータに基づいて解析されているかをよく確認することが重要です。
今後の展望
微小RNAは、がんだけでなく、糖尿病やアルツハイマー病など、他の様々な疾患のバイオマーカーとしても注目されています。今後、より精度の高い検査技術の開発や、治療効果の予測、再発のモニタリングなど、幅広い医療分野での応用が期待されています。