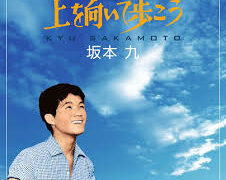かつて「避暑地」として知られた北海道も、今や猛暑が当たり前になりつつあります。30℃を超える日が続き、地域によっては40℃に迫るような予報が出ることも珍しくありません。このような猛暑を安全に乗り越えるためには、これまでの常識を覆すような、しっかりとした対策が必要です。
1. 涼しい場所の確保とクーリングシェルターの活用

自宅にエアコンがない場合や、エアコンがあっても節電のために使用を控えたい場合でも、暑さを我慢することは危険です。最寄りの公民館や図書館、ショッピングモールなど、涼しい公共施設や商業施設へ積極的に足を運びましょう。
最近では、自治体が「クーリングシェルター」を指定している場合があります。これは、住民が無料で涼める場所を確保する制度で、災害時の避難所とは異なり、一時的に涼をとることを目的としています。お住まいの地域の情報を確認し、いざという時の避難場所として頭に入れておくと良いでしょう。
2. こまめな水分補給は「のどの渇きを感じる前」に

熱中症予防の基本中の基本は、水分補給です。しかし、のどの渇きを感じてからでは遅いと言われています。特に高齢者の方はのどの渇きを感じにくくなるため、時間を決めて、こまめに水分を摂る習慣をつけましょう。
水、麦茶、スポーツドリンクなどが適しています。ただし、カフェインを多く含むコーヒーやアルコールは利尿作用があるため、水分補給には適しません。また、大量の汗をかいた際は、塩分を補給することも忘れずに。
3. 適切な服装と効果的な日差し対策

屋外に出る際は、服装を工夫するだけで体感温度が大きく変わります。吸湿性・通気性の良い綿や麻素材の服を選び、体の熱をこもらせないようにゆったりとしたシルエットのものがおすすめです。
直射日光を遮るための帽子や日傘は、もはや必需品です。特に日傘は、頭部に当たる日差しを遮ることで、体感温度を数度下げると言われています。最近では男性向けのシンプルなデザインの日傘も増えていますので、ぜひ活用してみてください。
4. 睡眠環境を整えて疲労回復を促す

夜になっても気温が下がらない熱帯夜は、睡眠不足の原因となり、翌日の体調不良につながります。寝具の選び方も重要です。麻や綿など、吸湿性・放湿性に優れた素材のシーツやタオルケットを使いましょう。
寝る前にぬるめのシャワーを浴びて体温を少し下げたり、扇風機を壁に向けて間接的な風を送ったりするのも効果的です。直接体に風を当てるよりも、部屋の空気を循環させることで、涼しさを感じやすくなります。
5. 食事と栄養で内側から熱に強い体づくり
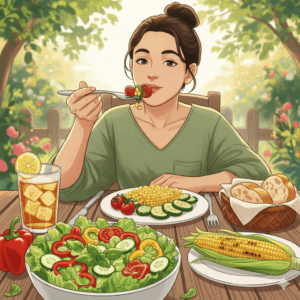
暑さで食欲が落ちがちですが、夏バテを防ぐためには栄養バランスの取れた食事が欠かせません。きゅうりやトマト、スイカなどの水分を多く含む野菜や果物は、水分補給にも役立ちます。また、梅干しや酢の物など、酸味のある食べ物は食欲増進効果が期待できます。
冷たいものばかりを摂りすぎると胃腸が弱ってしまうため、温かいスープや味噌汁を適度に取り入れることも大切です。
6. 熱中症のサインを見逃さず、早めの対応を
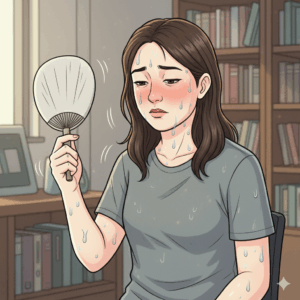
熱中症は、めまい、立ちくらみ、頭痛、吐き気、体がだるいといった初期症状から始まります。これらのサインを見逃さず、少しでも体調に異変を感じたら、すぐに涼しい場所へ移動し、体を冷やしてください。
重症化すると、意識障害やけいれんを引き起こすこともあります。意識がもうろうとしている、自分で水分補給ができないといった場合は、ためらわずに救急車を呼ぶことが重要です。
7. 高齢者、子ども、ペットへの特別な配慮
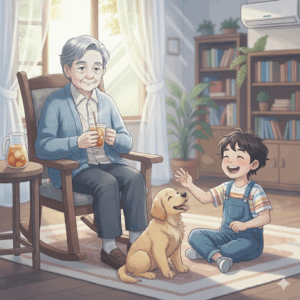
高齢者や子ども、ペットは、体温調節機能が未熟であったり、暑さを感じにくかったりするため、周囲が特に注意してあげる必要があります。
- 高齢者: のどの渇きを感じにくいため、定期的な水分補給の声かけが不可欠です。エアコンの使い方もためらわないよう促しましょう。
- 子ども: 地面からの照り返しを受けやすく、大人よりも体感温度が高くなります。こまめな休憩と水分補給、涼しい場所での遊びを心がけましょう。
- ペット: 室内でも熱中症になることがあります。エアコンや扇風機を使い、常に涼しい環境を保ちましょう。散歩は早朝や夜間に。
まとめ
北海道の気候が大きく変化するなか、これまでの「涼しい夏」というイメージは過去のものとなりつつあります。猛暑は誰にとっても危険であり、熱中症は命に関わる問題です。
こまめな水分補給、涼しい場所での休憩、そして無理をしないこと。この三原則を意識するだけでも、熱中症のリスクは大きく減らすことができます。
自分だけでなく、周りの人や家族、ペットの様子にも気を配り、互いに声をかけ合い、助け合うことで、この厳しい夏を乗り越えていきましょう。