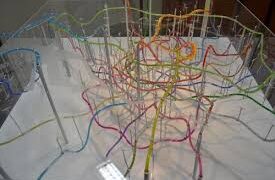「帝釈原人」は、広島県庄原市と神石高原町にまたがる帝釈峡(たいしゃくきょう)の遺跡群から発見された旧石器時代の人骨を指して使われる通称です。
帝釈峡遺跡群について
- 場所: 広島県の帝釈峡一帯に広がる石灰岩地帯にある洞窟や岩陰からなる遺跡群です。
- 特徴: 石灰岩地帯という特殊な環境のため、通常では腐って残りにくい人骨や動物の骨、貝殻などが良好な状態で保存されていました。これにより、旧石器時代から縄文時代、弥生時代に至るまでの人々の暮らしの変遷を詳細にたどることができる、貴重な遺跡群として知られています。
- 発掘調査: 1961年の帝釈馬渡岩陰遺跡の発見を皮切りに、広島大学が中心となって長年にわたり発掘調査が行われてきました。
「帝釈原人」と呼ばれた人骨
帝釈峡の遺跡からは、旧石器時代から縄文時代にかけての人骨が複数発見されています。特に、旧石器時代の人骨は日本国内でも最古級のものとされており、当時の人々の生活や身体的な特徴を知る上で重要な資料となっています。
「帝釈原人」という名称は、学術的な正式名称ではなく、メディアなどで通称として使われることが多かったようです。現在では、より正確な遺跡名や時代区分を用いて、学術的な文脈で議論されています。
帝釈峡遺跡群の出土品や調査の成果は、庄原市にある「庄原市帝釈峡博物展示施設 時悠館(じゆうかん)」などで見ることができます。