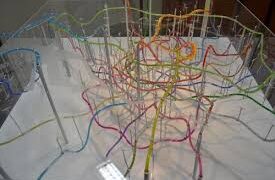木が紅葉(こうよう)する主な理由は、冬を迎える準備として葉を落とすためで、それに伴って葉の色を維持していた色素が変化するからです。
具体的には、気温の低下や日照時間の短縮がきっかけとなり、葉の中にある色素が変化します。
- 黄葉(おうよう)(イチョウなど):
- 葉の緑色の色素であるクロロフィルが分解されて少なくなります。
- 元々葉の中にあった黄色い色素のカロテノイドが目立つようになり、葉が黄色くなります。
- 紅葉(こうよう)(モミジなど):
- クロロフィルが分解されるのに加えて、新たに赤色の色素であるアントシアニンが合成されます。
- このアントシアニンが葉を赤く染めます。アントシアニンの合成には、日光がよく当たることが必要とされています。
- 褐葉(かつよう)(ケヤキなど):
- クロロフィルが分解され、茶色の色素であるフロバフェンなどが増えることで、葉が茶色くなります。
木は、葉が落ちる前に、葉の中に残っている光合成でつくられた養分(栄養)を幹などに回収します。この養分を回収する過程で、葉の細胞を守るためにアントシアニンが生成される、といった説もあります。
※クロロフィルとは、主に植物や藻類に含まれる緑色の色素で、「葉緑素(ようりょくそ)」とも呼ばれます。
このクロロフィルがなくなることで、今まで緑色に隠れていた黄色い色素(カロテノイド)や、新たに作られる赤い色素(アントシアニン)、褐色の色素(フロバフェン)が目立つようになり、葉が黄色や赤、褐色に色づく紅葉が起こります。