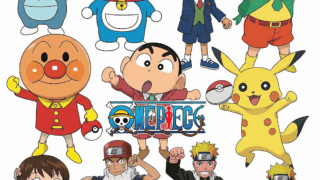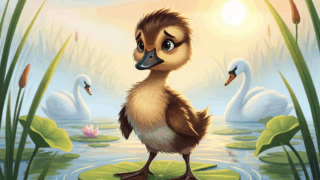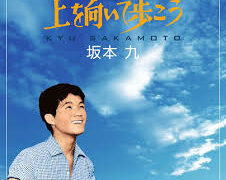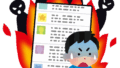人が昔の物理的な痛みを忘れる、あるいは「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ようにその感覚が薄れていく現象は、脳が持つ情報の取捨選択機能と、痛みの信号が持つ本質的な役割に深く関わっています。
ここでは、そのメカニズムを3つの観点から分析します。
1. 痛みの信号の役割の終了(急性痛の場合)
身体が感じる痛みには、「急性痛」と「慢性痛」があります。昔の痛みを忘れる現象は、主に急性痛のカテゴリーで見られます。
- 痛みの本質的な役割: 急性痛は、身体の損傷や危険を知らせるための**「警報信号」**としての役割を持っています。この警報は、「今すぐ対処せよ」という生存に必要な情報であり、だからこそ、その瞬間の痛みの感覚と恐怖は扁桃体によって強く記憶されます。
- 役割の終了と記憶の減衰: 怪我や病気が治癒し、身体の損傷がなくなると、痛みの原因が取り除かれます。脳にとって、その信号はもはや「今対処すべき危険」ではなくなります。警報の必要性がなくなると、その痛みの**「感覚的な強さ」に関する記憶は、他の多くの感覚情報と同様に、時間とともに重要度が低下し、徐々に減衰**していきます。
2. 記憶の「分離」と感覚的な側面の風化
痛みの記憶は、「感覚的側面」と「情動的側面」に分かれて脳に記録されるため、この分離が痛みの感覚を忘れやすくします。
- 感覚記憶の風化: 痛みの「場所や強さ」といった感覚的側面を処理する一次体性感覚野の情報は、時間の経過とともに薄れやすい傾向があります。私たちは、その日の服装の色や食べた昼食の具体的な味といった感覚情報は日常的に忘れていきます。痛みも、その「感覚」だけを取り出せば同様に風化していくのです。
- 情動記憶の持続: 一方で、痛みを伴う「恐怖」や「苦痛」といった情動的側面は、扁桃体によって強化されたため、感覚的な詳細が薄れた後も、「あの時は大変だった」「もう二度と経験したくない」という**強い感情の記憶(情動記憶)として長く残ります。人は「痛かったという事実」と「その時の苦しい感情」は覚えていても、「痛みそのものの感覚」**は再現できなくなります。
3. 脳の「防衛メカニズム」と意識的な抑制
脳には、不要な、あるいは有害な情報から心を守るための防衛的な機能も備わっています。
- 精神的防御としての忘却: あまりにも強烈で苦痛な記憶(特にトラウマ的な記憶)は、心を守るために無意識的に記憶のアクセスを困難にする**「解離」という防衛機制が働くことがあります。そこまでいかなくとも、日常生活を送る上で、過去の強烈な痛みの感覚を常に鮮明に思い出すことは、精神的な負担が大きすぎます。脳は、積極的にその苦痛な感覚情報を意識の表面から遠ざける**方向に働きます。
- 「今」の優先: 脳は常に、**「今」**の環境や課題に集中し、生存に最も関連性の高い情報を優先的に処理します。過去の痛みの感覚は、新しい情報や現在の生活の出来事によって上書きされ、処理の優先順位が下がっていきます。
このように、人は昔の物理的な痛みを忘れるのは、その痛みの警報としての役割が終わり、記憶の中でも感覚的な部分が風化しやすい性質を持ち、さらには脳が精神的な防御のために無意識的にその感覚を遠ざけようとするためだと言えます。