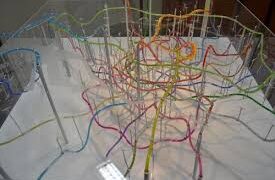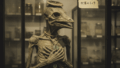安藝ノ海関は、大正3年(1914年)に広島県広島市で生まれ、出羽海部屋に入門しました。順調に番付を上げ、昭和13年(1938年)1月場所に新入幕を果たします。
そして迎えた昭和14年春場所4日目。この日、双葉山関は、前人未到の70連勝がかかる大一番に臨みました。双葉山関は前回の敗戦(昭和11年)から3年以上、誰にも負けを知らない「不滅の横綱」として、まさに神格化された存在でした。対する安藝ノ海関は、入幕してまだ2場所目の新鋭。誰もが双葉山関の勝利を疑いませんでした。
しかし、この日の安藝ノ海関は、師匠である出羽海一門一丸となって練られた、双葉山対策を見事に実行します。軍配が返ると同時に突っかけ、頭を下げて低く突っ張り、得意の左四つを狙う双葉山関に右前褌(みたまえみつ)を取って食い下がります。非力と言われながらも、この一番に懸ける気迫はすさまじく、「相手はみんなウジ虫だと思って土俵に上った」と後に本人が語るほどの負けん気の強さを見せました。
⚡ 勝利の瞬間と横綱への道
両者、がっぷり四つの状態から、双葉山関が強引に右から掬い(すくい)投げに出た瞬間、安藝ノ海関は双葉山関の腰が伸びたところを逃さず、会心の一撃、外掛けで双葉山関を土俵に這わせました。その瞬間、国技館は水を打ったような静寂ののち、地鳴りのような大歓声に包まれたといいます。
この大金星によって、安藝ノ海関は一躍、全国的な英雄となりました。この「打倒・双葉」の一番を境に、彼の相撲人生は大きく飛躍します。自信をつけた安藝ノ海関は、その後も粘り強い相撲で番付を上げ続け、昭和17年(1942年)5月場所後の横綱昇進を果たし、第37代横綱に名を連ねました。
🕊️ 気迫と速攻、そして「一番相撲の名人」
安藝ノ海関の相撲は、非力な体格を気力と技術で補うものでした。左四つを得意とし、前褌を取って食い下がり、右からおっつけながら攻める速攻相撲が持ち味でした。特に、ここ一番の大勝負に強く、「一番相撲の名人」とも呼ばれました。
横綱昇進後も、双葉山関と幾度となく名勝負を繰り広げ、昭和大相撲史に多大なドラマを提供しました。通算成績は209勝101敗38休、幕内では142勝59敗38休、幕内最高優勝1回という記録を残しています。
戦時下の苦しい時代を、その気迫溢れる相撲で人々に勇気を与え続けた安藝ノ海関。彼の力士としての功績はもちろん、双葉山関の連勝を止めたという不滅のエピソードは、今なお大相撲の語り草として、熱く語り継がれています。
引退後、年寄・藤島を襲名した後、解説者としても活躍し、晩年は悠々自適な生活を送ったとされていますが、彼の名を大相撲史に永遠に刻み込んだのは、やはりあの「69連勝ストップ」の瞬間でしょう。