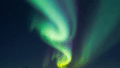ラ・ラ・ランド[オリジナル・サウンド・トラック]
はじめに
映画史に残る傑作ミュージカル『ラ・ラ・ランド』。その感動を色鮮やかに彩るのが、ジャスティン・ハーウィッツによる珠玉のオリジナル・サウンドトラックです。映画を観た方はもちろん、音楽だけでもその魅力に引き込まれること間違いなし。今回は、『ラ・ラ・ランド [オリジナル・サウンドトラック]』の全貌を徹底的にレビューし、その音楽がどのように物語を昇華させているのか、その魅力を深掘りしていきます。心躍るメロディー、切ないハーモニー、そして夢を追いかける登場人物たちの感情が詰まったこのサウンドトラックは、あなたの日常に鮮やかな色彩と感動を与えてくれるでしょう。さあ、ラ・ラ・ランドの音楽の世界へ、一緒に足を踏み入れてみましょう。

ベネチア国際映画祭
観客賞受賞
『ドライヴ』
ライアン·ゴズリング
日本アカデミー賞
最優秀外国作品賞
本年度アカデミー賞
最多6部門受賞!
監督賞 主演女優賞(エマ·ストーン) 撮影賞 美術賞 作曲賞 主題歌賞(City of Stars)
ゴールデン·グローブ賞 歴代最多7部門受賞
トロント国際映画祭
女優賞(エマ·ストーン)受賞
『セッション』監督·脚本最新作
『アメイジング·スパイダーマン』シリーズ
エマ·ストーン
LA LA LAND
ラ·ラ·ランド


世界に興奮と熱狂を叩きつけた『セッション』監督最新作は、 本年度アカデミー賞®大本命の 極上のミュージカル・エンターテイメント!
伝説の第2章が、胸が高鳴る華やかな音楽と共に幕を開けた! アカデミー賞®を含む50を超える賞を受賞し、日本でも「かつてない衝撃」と劇的なブームを巻き起こした『セッション』から2年、全世界熱望のデイミアン・チャゼル監督の最新作が遂に完成した。 映画と恋におちた若き天才が新たに創り出したのは、歌・音楽・ダンス・物語─すべてがオリジナルにして圧巻のミュージカル映画。この鮮やかでどこか懐かしい映像世界で、一度聞いたら耳から離れないメロディアスな楽曲に乗せて繰り広げられるのは、リアルで切ない現代のロマンス─。
夢追い人の街L.A.(ロサンゼルス)、 売れないジャズピアニスト:セブと女優志望:ミアの恋の行方は─? 再び映画史を変える、予想だにしない大仕掛けが、 観るもの全てを〈ラ・ラ・ランド〉へと誘う。
STORY
夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼルス。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指していたが、何度オーディションを受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピアニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ(セバスチャン)、いつか自分の店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二人は恋におち、互いの夢を応援し合う。しかし、セブが店の資金作りのために入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる……。


映画「LA LA LAND(ラ・ラ・ランド)」に登場するLAのスポットをご紹介!
ロサンゼルスが舞台の『ラ・ラ・ランド』。エマ・ストーン演じるミアとライアン・ゴズリング演じるセバスチャンがロサンゼルスの街で、恋に惹かれ合うロマンチックなミュージカル映画です。
ダミアン・チャゼルが脚本と監督を務めた『ラ・ラ・ランド』は、アカデミー賞で14ノミネートされ、『イヴの総て』(1950年)と『タイタニック』(1997年)に並ぶ1作品での最多ノミネートを記録しています。第89回アカデミー賞では、ラ・ラ・ランドはチャゼル監督の監督賞(同部門最年少受賞)、主演女優賞(エマ・ストーン)、オリジナル楽曲賞(「City of Stars」)を含む6部門を受賞しました。 『ラ・ラ・ランド』のロケ地を巡るロサンゼルスで、どんな魔法の体験が待っているのかご紹介しましょう。
- グリフィスパーク
- グリフィス天文台
- エンジェルズ・フライト
- サリタズ・ププセリア
- ワッツ・タワー
- ザ・ライトハウス・カフェ
- ハモサビーチ・ピア
- スモークハウス・レストラン
- コロラド・ストリート・ブリッジ
- 同業者が同業者をたたえる賞
- ”聖地巡礼”したくなる、ハリウッド愛全開の作品
- 往年の映画作品の技法をふんだんに“引用”
- 昨年の反省やトランプ政権が結果に影響?
- 【構造・衣装・心情】『ラ・ラ・ランド』が私たちに見せてくれた、夢
- 古き良きハリウッド感ミーツ現代
- ショットの構造から読み解く心情
- カラフルな衣装が意味するもの
- 全収録曲レビュー:夢と情熱の旋律
- Another Day Of Sun (LA LA LAND CAST)
- Someone In The Crowd (Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe)
- Mia & Sebastian’s Theme (Justin Hurwitz)
- A Lovely Night (Ryan Gosling, Emma Stone)
- Herman’s Habit (Justin Hurwitz)
- City of Stars (Ryan Gosling)
- Planetarium (Justin Hurwitz)
- Summer Montage / Madeline (Justin Hurwitz)
- City of Stars (Ryan Gosling, Emma Stone)
- Start A Fire (John Legend)
- Engagement Party (Justin Hurwitz)
- Audition (The Fools Who Dream) (Emma Stone)
- Epilogue (Justin Hurwitz)
- The End (Justin Hurwitz)
- City of Stars (Humming) (Justin Hurwitz featuring Emma Stone)
- サウンドトラックが映画体験を深める理由
- 『ラ・ラランド』登場人物と出演者たち
- 解説・あらすじ
グリフィスパーク
グリフィス・パークは、4,300エーカー以上の広さを誇る、全米で11番目に大きな市営の公園です。ハリウッド・ヒルズでのパーティーの後、セバスチャンとミアはサンフェルナンド・バレーの絶景を背景にショーストッパーの “A Lovely Night” のダンスシーンを披露。このシーンは、マウント・ハリウッド・ドライブから離れた “Cathy’s Corner “で、何と1テイクで撮影されました。

グリフィス天文台
ロサンゼルスを象徴する文化的な建物の一つグリフィス天文台は、テレビ番組や映画のロケ地として有名ですね。最も有名なのは、ジェームズ・ディーンとナタリー・ウッドが主演した『理由なき反抗』(1955年)でしょう。サミュエル・オシン・プラネタリウムでのセバスチャンとミアのシーンは印象的でしたね。

エンジェルズ・フライト
セバスチャンとミアは、LAのダウンタウンにあるグランド・セントラル・マーケットの向かい側、ヒル・ストリートにあるランドマーク、エンジェルズ・フライトに乗ります。当時、エンジェルズ・フライトは閉鎖されていましたが、映画製作の為、1日だけ使用する許可を得たとのこと。
その他、ノワール映画の『クリス・クロス』(1949年)や『キス・ミー・デッドリー』(1955年)、テレビドラマの『ボッシュ』『ペリー・メイソン』(原作と2020年のHBOシリーズ)、『ドラグネット』など100以上の映画で登場します。

サリタズ・ププセリア
1917年にオープンしたグランド・セントラル・マーケットには、世界各国の伝統的な料理からモダンな料理まで、沢山の屋台が並び活気にあふれています。映画のシーンで、セバスチャンとミアがサリタズ・ププセリアに立ち寄るシーンを覚えていますか。サリタのププサは、ベジタリアン向けのメニューも含め、数十種類の具がいっぱい入った手作りのププサを提供しています。

ワッツ・タワー
世界的に有名なワッツ・タワーは、1921年から1954年までの33年間、イタリア移民の建設技師サバト・ロディア(別名サム、サイモン)によってコツコツと造られました。ロディアは、手動の工具と窓拭きの道具だけを使い、たった一人で塔を建てたのです。1990年に国定歴史建造物に指定され、「ドラムの日」フェスティバルや「サイモン・ロディア・ワッツ・タワーズ・ジャズ・フェスティバル」などのイベントが毎年開催されています。 注:ワッツタワーズは現在改修中のため、立ち入ることができません。アートセンターは工事中も一般公開されています。

ザ・ライトハウス・カフェ
『ラ・ラ・ランド』では、ジャズの場面が沢山出てきます。セバスチャンは自分のクラブを開くことを夢見ながら、カクテルパーティーの演奏で生計を立てているジャズピアニスト。ハーモサビーチのザ・ライトハウス・カフェは、1949年5月からジャズバーとして、マイルス・デイビス、チェット・ベイカー、アート・ブレイキー、キャノンボール・アダレイといった伝説的なミュージシャンを輩出しています。現在では、ジャズからレゲエ、ロックまで、幅広いジャンルの音楽が演奏されています。

ハモサビーチ・ピア
太平洋に伸びるハモサビーチ・ピアは、フィッシングや美しいサンセットで人気の場所です。ミアと一緒にザ・ライトハウス・カフェを訪れた後、セバスチャンはピアを散策し、アカデミー賞受賞曲 “City of Stars” を歌い上げます。

スモークハウス・レストラン
1946年の創業以来、スモークハウス・レストランは、ワーナーブラザーズに近いこともあり、エンターテインメント業界の人々で賑わっています。この伝説のステーキハウスは、セバスチャンがホリデーソングを演奏するサパークラブの代わりを果たしています。

コロラド・ストリート・ブリッジ
1913年の完成以降、世界で最も高いコンクリートの橋と言われているコロラド・ストリート・ブリッジ。開通当時から旅行者や地元の人々に愛され、空に向かって伸びる15mの壮大なアーチは、ロサンゼルスで最もロマンチックなランドマークの一つとなっています。
若き天才デイミアン・チャゼルが、『ラ・ラ・ランド』で成し遂げたこと

1985年生まれの、デイミアン・チャゼル。ハイスクール時代はミュージシャンを目指してジャズを学ぶが、ハーバード大学に進む頃には、幼き日の夢だった映画監督への想いが甦る。チャゼルは貪るように古今東西の映画を観まくったというが、そんな中でも、“ミュージカル映画”に夢中になった。
本作『ラ・ラ・ランド』(2016)のアイディアが浮かんだのは、ハーバード在学中。チャゼルは学友で、その後共に歩むことになる、作曲家ジャスティン・ハーウィッツと、ストーリーを練り始めた。
そのハーウィッツと共に、ハーバードの卒業製作として作り上げたのは、16mmフィルムで撮影した、全編モノクロのミュージカル『Guy and Madeline on a Park Bench』(2009)。ジャズに執心する主人公Guyのキャラクターは、チャゼルのその後の作品にも、引き継がれていく。
この卒業製作が評判となり、小規模ながら劇場公開に至った。ちょうどその頃、2010年にチャゼルは、『ラ・ラ・ランド』の脚本初稿を書き上げる。
プロデューサーを雇っての売込みに、『ラ・ラ・ランド』に興味を持つ製作会社が現れた。しかし、主人公が愛する音楽をジャズでなくてロックに変更することや、オープニングの曲の差し替え等を求められたため、プロジェクトは頓挫する。
チャゼルは、方針を転換。商業映画デビュー作としては、『ラ・ラ・ランド』よりは低予算でイケる、『セッション』(14)に、取り組むことにした。
ハイスクール時代の自身の経験も多く盛り込んだという『セッション』は、名門音楽学校に入学した若きドラマーと伝説の鬼教師の攻防を、息も突かせぬド迫力で描いた作品。
330万ドルの製作費に対し、世界中で5,000万ドルの興行収入を上げ、またその年度のアカデミー賞で、5部門にノミネートされた。結果として、作品賞及びチャゼルがノミネートされた脚色賞は逃したものの、鬼教師を演じたJ・K・シモンズに助演男優賞、更に編集賞、録音賞の計3部門での受賞となった。
『セッション』をリリースした際、まだ30歳になる前だったチャゼルは、「若き天才」との呼称を恣にする。ここに、『ラ・ラ・ランド』映画化の機は熟した。製作会社のライオンズゲートに提案すると、製作費3,000万㌦を掛けて、チャゼルが思い描いた通りの内容で撮れることになったのだ。
当初主役のカップルには、エマ・ワトソンと、『セッション』の主演だったマイルズ・テイラーの名が挙がった。しかしワトソンは、ディズニーの実写版『美女と野獣』(17)ヒロインのオファーを選ぶ。そしてテイラーとの交渉も不調に終わったため、新たなキャスティングが進められることとなった。決まったのは、同じエマでも、エマ・ストーン、そしてライアン・ゴズリングである。

クリスマスが近くても暑い、冬のロサンゼルス。
女優になる夢を叶えるためこの街に来たミア(演:エマ・ストーン)は、映画スタジオ内のコーヒーショップに勤めながら、様々なオーディションを受ける日々。
ある日、ピアノの音色に誘われて足を踏み入れたレストランで、その奏者に感動を伝えようとする。しかし当のピアニスト、セブことセバスチャン(演:ライアン・ゴズリング)は、店長の指示に従わず、勝手な曲を演奏したため、その場でクビに。セブは近寄ってきたミアを無視し、店外へと消えた…。
春が訪れ、ミアとセブは再会。偶然の出会いが続き、2人は言葉を交わすようになる。
「時代遅れ」と揶揄されるようなジャズをこよなく愛するセブの夢は、いつか好きな曲を好きなだけ演奏する、自分の店を持つこと。お互いの夢を熱く語り合う内に、2人は惹かれ合い、やがて結ばれる。
夏が来る頃には、ミアとセブは同棲。互いの夢を支え合い、幸せの絶頂にいた。
生活のための術が必要と考えたセブは、かつての音楽仲間が組んだバンドに、キーボード奏者として参加。その楽曲は、セブが愛するフリージャズとはかけ離れており、ライヴに出向いたミアは、戸惑いを覚える。
しかしバンドは大人気となり、セブはツアーやレコーディングで多忙に。2人は、会えない時間が多くなる…。
秋。ツアーを抜け出して、ミアにサプライズを仕掛けたセブ。しかしミアのちょっとした一言から、大喧嘩となってしまう。
そんな折り、ミアがセブの勧めで書き上げたひとり芝居が、幕を開ける。しかし客席はガラ空き。公演後には酷評が耳に届く。打ちのめされたミアは、仕事のため公演に間に合わなかったセブに、「何もかも終わり」と告げ、故郷に帰ってしまう。
数日後、ひとり残されたセブの元に、ミアを探す配役事務所から電話が入るが…。
*****
ミア役のエマ・ストーンは、ブロードウェイでミュージカル「キャバレー」に出演。評判になったのを受けてのキャスティングだった。
チャゼルは、セブ役にライアン・ゴズリングを得たことを、本作の「製作の長いプロセスのキーになった」ポイントとして、挙げている。
ストーンとゴズリングの共演は、『ラブ・アゲイン』(11)『L.A. ギャング ストーリー』(13)に続いて、本作で3度目。そのすべてでカップルを演じている2人の相性が、フレッド・アステア&ジンジャー・ロジャース、ハンフリー・ボガート&ローレン・バコール、マーナ・ロイ&ウィリアム・パウエルといった、ハリウッドの伝説のカップルのように、「しっくり合っている」と、チャゼルには感じられたのだ。
撮影前の準備期間、ゴズリングはジャズ・ピアノを、3ヶ月練習。その成果として、本作では全編、本人による演奏が見られる。手元のクローズアップでも、代役は使っていない。
セブが加入するバンドのリーダーを演じた、ミュージシャンのジョン・レジェンドは、ゴズリングのあまりの習得の早さに驚愕。嫉妬すら覚えたという。
ピアノと同時に、ゴズリングはエマ・ストーンと、ダンスの練習にも励んだ。ストーン曰く、2人は売れないアーティストの役なので、圧倒的な歌唱力やダンスといったものは、「求められなかった」という。2人の関係がある意味では未熟に見えることを、チャゼルが望んだが故である。

さて本作のタイトル『ラ・ラ・ランド』は、チャゼルによると、ロサンゼルスを「からかうような感じで呼ぶとき」に使うという。それに加えて、空想にふけるという意味もあり、夢を見るのはすてきなことだというメッセージも籠めたのである。
そんな『ラ・ラ・ランド』は、40日間掛けて、グリフィス天文台から歴史あるジャズクラブまで、ロサンゼルスの各所でロケ撮影が行われた。
チャゼルが愛する、1930年代から50年代に掛けての、アステア&ロジャースやジーン・ケリーが主演したミュージカルは、スタジオにセットを組み、先に歌声を録音した楽曲を流しながら、ダンスシーンを撮った。しかし本作は、ロケ地で演者が歌って踊り、生歌を同時に録音する方式で、撮影が行われた。
しかもすっかりデジタル撮影が主流になっていたこの時代に、フィルムを使用。並大抵の準備では、済まなかった。
オープニングのつかみとなる、ハイウェイの大渋滞を縫っての群舞シーン。警察の協力で、高速道路を封鎖して、ロケが行われた。
驚異のワンカット撮影を、限られた時間で行わなければならないため、スタジオの駐車場に、作り物の分離帯や車を沢山置いて、丁寧にリハーサル。いざ本番は、気温が43度という猛暑の中で行われた。
一発OKとはいかないため、撮影が終わる度にダンサーたちはアシスタントに抱えられて、スタート地点に戻る。そして汗を拭き取り予備の衣装に着替えてから、リテイクに臨んだという。
因みに本作の振り付けを担当したのは、TVのミュージカルドラマ「glee/グリー」で評判をとった、マンディ・ムーア。高速道路のシーンでは、撮影中に写り込んでしまうことを避けるため、車の下に隠れて指示を出したという。
ハリウッドの丘の上で、ストーンとゴズリングが踊るシーンも、現地ロケ。日没直後のマジックアワーを狙ったため、撮影のチャンスは、2日間で30分ほど。そんな中で2人は、長回しのダンスシーンを、繰り返し撮影した。

先に記した、ハリウッド黄金期のミュージカル以上に、チャゼルが影響を受けたのは、実はフレンチ・ミュージカル。ジャック・ドゥミー監督、ミシェル・ルグランが音楽を担当した『シェルブールの雨傘』(1964)こそが最大級の意味で、「僕を成長させてくれた映画」と、語っている。そして当然のように本作でも、オマージュが捧げられている。
その一方でチャゼルが腐心したのは、ノスタルジックや演劇的になり過ぎないようにすること。曰く、「ミュージカルには他のジャンルにない楽しさ、高揚感があるけれど、同時に現実的で正直なストーリーが必要だ。ファンタジーとリアルがね」
ファンタジーとリアル/夢と現実が一体となった、新しいミュージカル映画のスタイルを作り出すための一助となったのが、マーティン・スコセッシ監督のボクシング映画『レイジング・ブル』(80)。この作品では、カメラをボクシングのリング内に持ち込んで、常にボクサーの動きに焦点を合わせる形で、撮影が行われている。スコセッシは、リング上では観客がボクサーの眼を持ち、殴られているのは自分だという意識を持たせるために、この手法を考案した。
これを「表現主義的なカメラワーク」と言うチャゼルは、スコセッシがリングの中にカメラを置いたように、自分はダンスの中にカメラを置きたかったと語っている。
スコセッシ作品からの影響という意味では、『ニューヨーク・ニューヨーク』(77)も忘れてはいけない。この作品でカップルを演じたのは、ライザ・ミネリとロバート・デ・ニーロ。ミネリは無名の俳優からハリウッドの大スターに、デ・ニーロは売れないサックス奏者からジャズ・クラブのオーナーへと成功の道を歩みながら、別れ別れとなっていく。『ラ・ラ・ランド』のミアとセブの軌跡は、『ニューヨーク・ニューヨーク』の2人の歩みと、ほぼほぼカブる。
さて本作『ラ・ラ・ランド』の別れた2人は、ラスト近くになって、5年振りに再会。そこで実際にはそうならなかった、2人が添い遂げる人生が、イメージの中で展開する。
チャゼルが「ただの夢じゃない」と語るこのシーン。たとえ今は別々の人生を送っていても、あの時2人で愛し合った、素晴らしき時間があったからこそ、今の自分たちがある。「あり得た人生」を想うのは、単なる後悔ではなく、希望ともなる…。

『ラ・ラ・ランド』はクランクアップから、編集に1年掛けて完成。まずは2016年秋の「ヴェネチア映画祭」オープニング作品として、大きな話題をさらった。
その後本国アメリカで大ヒットを記録すると同時に、各映画賞で受賞ラッシュとなる。その本命と言うべき、2017年2月に開催されたアカデミー賞では、史上最多タイの14ノミネート。監督賞、主演女優賞など6部門で受賞を果したが、それ以上に前代未聞のアクシデントに巻き込まれたことが、大ニュースとなった。
この年の“作品賞”のプレゼンター、ウォーレン・ベイティが受賞作品の封筒を開け、『ラ・ラ・ランド』と発表を行った。しかし受賞スピーチが始まった直後に、これがスタッフのミスによる封筒取り違えと判明。改めて『ムーンライト』(16)に“作品賞”が与えられるという、大珍事が起きてしまったのだ。
“作品賞”という大魚を逃しながらも、それ以上にインパクトの残る形で、記録や記憶に残った、『ラ・ラ・ランド』。それもまたデイミアン・チャゼル、当時の「若き天才」ぶりに贈られた、勲章のようにも思える。■
改めて振り返る『ラ・ラ・ランド』、そしてこの“ミュージカル”作品が映画界に与えた影響
「LA LA LAND Live in Concert : A Celebration of Hollywood ハリウッド版 ラ・ラ・ランド ザ・ステージ」と題されたイベントが8月に開催される。
これまでロサンゼルス以外では一度も行われていないこのフィルム・コンサートは、『ラ・ラ・ランド』のスクリーン上映に、16名のダンサー、60名の大合唱団、88名編成のフルオーケストラとジャズ・バンドの生演奏に、花火などの特殊効果が加わったスペシャルなもの。しかも同作の作曲を担当したジャスティン・ハーウィッツが指揮者として参加するという。ロサンゼルスのハイウェイを、実際に一時封鎖してロケ撮影されたオープニング・シーンで幕を開ける壮大な映画に相応しいイベントではないか。
それにしても公開後たった6年で、このようなイベントが行われるほど、傑作認定されている『ラ・ラ・ランド』をハーウィッツと作り上げた監督兼脚本家のデイミアン・チャゼルとは一体どんな人物なのだろうか?
デイミアン・チャゼルとは?
デイミアン・チャゼルは1985年生まれ。名前の響きがフランスっぽいのは、父親がフランス出身だからだ。彼の作品にジャック・ドゥミやミシェル・ルグランからの影響が見え隠れするのは、こうしたルーツにあるように思える。
幼い頃から映画製作を夢見ていたチャゼルだったが、同じくらいジャズにも夢中になり、高校時代は全米高校ビッグバンド選手権の常連校でドラマーとして活躍していたという。しかし部活の顧問との軋轢で疲弊してしまい、進学先のハーバード大学では映画製作を専攻することにした。
その大学の寮でルームメイトになったのが、前述のハーウィッツだった。脚本家志望だった彼もジャズピアノを学んでいたことから、ふたりは意気投合。学内で結成されたロックバンド、チェスター・フレンチで演奏しながら(後にチェスター・フレンチはふたり抜きでメジャーデビューしたが、チャゼルはアルバム『Love The Future』にドラマーとして参加している)、ミュージカル映画作りの夢を語り合ったという。
それが最初に結実したのが、卒業論文の一部として製作した、監督&脚本チャゼル、音楽:ハーウィッツがによるミュージカル映画『Guy and Madeline on a Park Bench』(2009)だった。
ジャズ・トランペッターを夢見る男と女の恋愛を描いたこの作品は、トライベッカ映画祭に出品され、チャゼルたちがハリウッドで注目されるきっかけをもたらした。現在、サントラは配信で聴くことが出来るが、『ラ・ラ・ランド』以上にミシェル・ルグランに傾倒したフレンチ・テイストなサウンドが印象的だ。
ジャズとミュージカル映画への愛
チャゼルとハーウィッツは、同作をアップグレードした本格的なミュージカル映画の製作を望んだが、完全オリジナルのミュージカル映画に出資するプロデューサーはなかなか現れない。やむなくチャゼルは高校時代の部活体験をもとにした映画を監督第二作として発表した。それが『セッション』(2014)である。主演は最近『トップガン マーヴェリック』(2022)で大量の新規ファンを獲得したマイルズ・テラーだった。
テラーの熱演もあいまってスマッシュヒットを記録した『セッション』だったが、そこで描かれたジャズ観を「古い」と批判する声もあったのも事実である。しかしそれは見当違いというものだ。チャゼルは、あくまで「過ぎ去った過去の音楽」としてのジャズを愛しているのだから。
それはミュージカル映画についても同じである。「既に終わってしまった華やかなもの」だからこそ、チャゼルはこのジャンルを偏愛しているのだ。そんなジャズとミュージカル映画への彼の愛をそれぞれ人格化させた存在が、『ラ・ラ・ランド』の主人公セブとミアなのである。
こうした経緯を踏まえて『ラ・ラ・ランド』を観ると、ミアがクライマックスで歌う「オーディション」の「Here’s to the Ones Who Dream Foolish As They may Seem(どうか乾杯を、愚かな夢を見る者たちに)」という歌詞が、時代錯誤なヴィジョンに賭けたチャゼルが自分を鼓舞するために作ったかのように思えてくる。しかしこうした無謀な挑戦にチャゼルとハーウィッツは勝利を収めた。『ラ・ラ・ランド』は世界中で大ヒットを記録して、ミュージカル映画というジャンルをリフレッシュさせたのだから。
『ラ・ラ・ランド』で生まれた新しい流れ
こうした新しい流れに乗った代表的なクリエイターが、『ラ・ラ・ランド』で作詞を担当したベンジ・パセック&ジャスティン・ポールである。もともと作曲もこなすチームだった彼らは、『ラ・ラ・ランド』の翌年に早くも自身のオリジナル・ミュージカルを発表する。それがヒュー・ジャックマン主演の『グレイテスト・ショーマン』(2017)である。19世紀に活躍した伝説的な見せ物小屋興行師、P・T・バーナムをピュアな夢想家として描くという離れ業をやってのけた同作からは「This Is Me」というクラシック・チューンが誕生した。
同作の大ヒットによって、ふたりのブロードウェイにおける出世作『ディア・エヴァン・ハンセン』(2021、舞台初演は2015)も、舞台版でも主役だったベン・プラットを主演に迎えて映画化された。同作が描くのは、SNSの流行によってペルソナを被らざるをえなくなり、孤独を募らせていく現代のティーンの葛藤だ。
劇中では、こうしたテーマに即したエモーショナルなパワーポップ・チューンが次々と歌われる。エヴァンが高校への登校中に「いつまで窓の中から景色を見ていなければいけないんだ」と歌う冒頭曲「Waving Through A Window」から、「たとえ闇が押し寄せてきても誰かが見つけてくれる、抱えてくれる友人が必要なら誰かが見つけてくれる」と訴える「You Will Be Found」まで、現役ティーンなら(退役ティーンも)感涙必至だろう。
リン=マニュエル・ミランダ
『ディア・エヴァン・ハンセン』でメガホンを取ったのは、『ウォールフラワー』(2012)の原作者兼監督で知られるスティーヴン・チョボスキーだったが、映画版『レント』(2005)の脚本家でもあったことも監督に選ばれた理由だったはずだ。『レント』の作者であるジョナサン・ラーソンこそは、同時代のポップミュージックをミュージカルに持ち込んだ革新者だったからだ。
ラーソンは35歳の若さで亡くなったが、彼がやろうとした事を現在のブロードウェイで受け継いでいる存在が、アメリカ建国の立役者をラップで描いた『ハミルトン』で知られるリン=マニュエル・ミランダである。
才能の塊のようなミランダだが、ミュージカル映画への進出は実に慎重だった。まずはディズニーアニメ『モアナと伝説の海』(2016)で挿入歌だけを担当(同作で好評を得た彼は『ミラベルと魔法だらけの家』(2021)でも楽曲を手がけてオスカーを獲得した)。続く『メリー・ポピンズ リターンズ』(2018)では音楽は手掛けず(楽曲を手がけたのはマーク・シャイマン)、俳優として、前作におけるディック・ヴァン・ダイク扮するバートのような立ち位置のジャックに扮し、歌い踊ってみせた。
そしてブロードウェイ公演時は自ら脚本、楽曲、主演の三役を務めた『イン・ザ・ハイツ』(2021)がついに映画化されたのだが、その際もミランダは、監督をジョン・M・チョウ、主演をアンソニー・ラモスに任せて、自身はプロデューサー(とチョイ役)に専念した。なぜ自分でやろうとしなかったのだろうか。そう、ミランダは膨大な人数のスタッフが関わる映画の撮影現場における様々な役割を、ひとつひとつ学んでいたのだ。
こうした学習の成果が現れたのが、前述のジョナサン・ラーソンが作った半自伝ミュージカルを映画化したミランダにとっての監督デビュー作『チック、チック…ブーン!』だった。スピーディーなカット割や、ミュージカル未経験だった主演のアンドリュー・ガーフィールドから、あれだけのパフォーマンスを引き出した演出力は賞賛に値する。
その『チック、チック…ブーン!』にもラーソンのメンターとして登場する『スウィーニー・トッド』(2007)や『イントゥ・ザ・ウッズ』(2014)で知られる作曲家スティーヴン・ソンドハイムが、2021年11月に亡くなった。ノア・バームバック監督作『マリッジ・ストーリー』(2019)で代表作『カンパニー』の挿入歌が重要な役割を果たし、出世作のリバイバル映画化作『ウェストサイド・ストーリー』(2021)の撮影を見届けての逝去だったため、大往生といえるのだが、ひとつの時代が終わった寂しさも感じる。
それでもショータイムは終わらない。現在ぼくが最も楽しみにしているミュージカル映画は、そのソンドハイムが1981年に手がけたブロードウェイ・ミュージカル『メリリー・ウィー・ロール・アロング』の映画化作品だ。オリジナルの舞台は、三人の旧友たちが曲を歌うごとに時を遡っていき、最後にティーンになるという前衛的なものだったが、監督のリチャード・リンクレイターはこれを『6才のボクが、大人になるまで。』方式で本当に20年間かけて撮影中なのだ(つまり初めの方に撮ったシーンほど後半のエピソードになる)。主演は前述のベン・プラットとビーニー・フェルドスタイン。公開は多分2040年頃である。
前代未聞!「ラ・ラ・ランド」の作品賞が”幻”に
2月27日(日本時間)に第89回アカデミー賞授賞式が行われ、13部門14ノミネートでオスカー最有力との下馬評も高かったデイミアン・チャゼル監督、ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン主演のミュージカル映画『ラ・ラ・ランド』は、監督賞や主演女優賞など6部門を獲得した。ただ発表の前から「受賞は間違いなし」といわれてきた作品賞は、ブラッド・ピットが製作総指揮を務めた『ムーンライト』に譲る結果になった。
さらに発表ではタイトルを『ラ・ラ・ランド』と読み間違える大ハプニングがあり、『ラ・ラ・ランド』は文字どおり“幻の作品賞作品”となった。アカデミー賞大本命といわれてきた作品に何が起こったのか。賞を決定するプロセスを振り返りながら、その理由を探ってみた。
同業者が同業者をたたえる賞
アカデミー賞は、6000人以上いるといわれているアカデミー会員による投票で決定する。このアカデミー会員とは、俳優、監督、技術職、プロデューサーなど映画業界に従事するプロフェッショナルたちで構成されている。俳優は俳優部門に、脚本家は脚本部門に、美術スタッフは美術部門に投票する仕組みで、つまり各部門賞は同業者の投票によって決定するというわけだ。そして作品賞だけは全会員の投票で決定する。いってみればアカデミー賞とは、「同業者が同業者をたたえる」ことを目的とした賞だといえる。
では、アカデミー会員とはどのような層なのだろうか。映画界における功績があれば国籍・居住地を問わずアカデミー会員として招待されるという規約があるが、以前の調査では会員の8割近くが「高齢の白人男性」だったと報告されるなど、しばしばその偏りが指摘されてきた。そして問題が大きく噴出したのは昨年のことだった。
前回の88回アカデミー賞でノミネートされた演技部門の俳優全員が白人だったことから(実はその前年もそうだった)、映画監督スパイク・リーや俳優のウィル・スミスが授賞式のボイコットを表明するなど、「白すぎるオスカー」としてその問題が表面化した。その反省もあって、米映画芸術科学アカデミーは、2020年までに多様な人種、女性の会員を増やすと宣言。手始めに、日本でも北野武、是枝裕和、黒沢清、河瀬直美、仲代達矢らに新たにアカデミー会員への招待状を送ったと報道された。
そして今年のノミネート作品を見ると、『ムーンライト』『フェンシズ(原題)』『ヒドゥン・フィギュア(原題)』『LION/ライオン~25年目のただいま~』といったアフリカ系アメリカ人やアジア人にスポットを当てた映画が数多くノミネートされた。そして、これらの映画からは「人種」の問題が色濃く浮かび上がっており、同時に排外主義的なドナルド・トランプがアメリカ大統領に就任した現状に対するアンチテーゼと見る論調もある。
”聖地巡礼”したくなる、ハリウッド愛全開の作品
もちろん政治的にこれらの作品・俳優が選ばれたわけではなく、どれを見ても作品の力で選ばれたのは紛れもない事実。それでもノミネート作品の傾向を見ると、近年、「人種の多様性」を標榜するハリウッドの自浄作用がきちんと働いていることが感じられる。
それでもまだまだ改革は道半ばで、「高齢の白人男性」がアカデミー会員の多数派である状況は今すぐには変わらない。そんな中、ハリウッドで働く多数のアカデミー会員にとって、『ラ・ラ・ランド』が謳(うた)いあげる「ハリウッドへの愛」は、彼らの心の琴線を刺激するには十分なテーマだったといえる。
サイレント映画のスターにスポットを当てた『アーティスト』(2012年の84回のアカデミー作品賞)や、映画撮影と偽ってイランからアメリカ大使館員を救出する『アルゴ』(2013年の85回アカデミー賞作品賞)など、ここ最近、銀幕や映画そのものを舞台にした作品が、アカデミー作品賞を取るケースが目立ってきている。『ラ・ラ・ランド』もその系譜に入る作品だろう。そう考えれば、作品を企画した段階からアカデミー会員に好まれる運命だった。
さらに、『ラ・ラ・ランド』には、ジェームズ・ディーン主演の『理由なき反抗』をはじめとした数多くの映画のロケ地となった「グリフィス天文台」や、映画『カサブランカ』で使われた「窓のセット」が組まれているワーナー・ブラザース・スタジオなど、ロサンゼルス各地で撮影を敢行している。思わず“聖地巡礼”をしたくなるようなロスの観光映画的な側面もある。そもそもタイトルの『ラ・ラ・ランド』とは、ハリウッド地域の愛称で、「陶酔し、ハイになる状態」「夢の国」という意味を持つ。当然こうしたシーンやタイトルが、アカデミー会員の“地元愛”をくすぐったことは間違いない。
そしてなんといっても、サンプリング世代ともいうべきチャゼル監督の“引用”の数々が映画を愛するアカデミー会員の研究心を刺激する。たとえばアメリカの雑誌『エンターテインメント・ウイークリー』のインタビューでチャゼル監督は、冒頭の高速道路での群舞シーンだけでも、マイケル・ダグラス主演の『フォーリング・ダウン』、ジャン=リュック・ゴダール監督の『ウィークエンド』、ジャック・ドゥミ監督の『ロシュフォールの恋人たち』、アルフレッド・ヒッチコックの『裏窓』、ルーベン・マムーリアン監督の『今晩は愛して頂戴ナ』、スタンリー・ドーネン監督の『掠奪された七人の花嫁』といった作品の影響があったことを明かしている。
往年の映画作品の技法をふんだんに“引用”
往年のハリウッド作品やフランスのクラシック映画を貪欲にかみ砕いて取り入れた作品は、深く掘れば掘るほどにはまり込んでしまう中毒性があるが、あくまでそれは物語を展開させるための彩りであり、そういった過去作を知らない人でも楽しめるところが、現在32歳ながら熟練した手腕を見せつけるチャゼル監督の真骨頂である。
撮影においても往年の映画への傾倒ぶりがうかがえる。「僕の手本は、(『輪舞』などで)映画史に名高いマックス・オフュルスの流麗なカメラワーク。ステディカム(スムーズな移動撮影を可能とするカメラ機材)のない時代にカメラを音楽のように、ダンサーのように動かした」「マーティン・スコセッシのボクシング映画『レイジング・ブル』のように、ボクシングのリングの中にカメラを置いたらどうなるか? 僕も同様にダンスの中にカメラを置きたかったんだ」と、監督が語るとおり、ダンスの中をカメラがダイナミックに動き、そしてカットを入れない長回しで、劇中のダンスの躍動感を余すことなく映し出す。
デジタル全盛の中、本作は35ミリフィルムでの撮影にこだわった。現在のシネマスコープサイズの横縦比は2.40:1だが、本作では往年のミュージカル映画で数多く使用された2.52:1の横縦比で撮影している。映画の冒頭にスクリーンが横に広がり、「シネマスコープ」のロゴが映し出される。チャゼル監督が、ミュージカル映画が持っていた魅力とそのエネルギーを現代に復活させたいという強い意志が感じられる。
本作のダンスシーンも、チャゼル監督は俳優自身の肉体で一気に長回しで撮ることにこだわった。本作の主演を務めるエマ・ストーン、ライアン・ゴズリングらも本作で実際にダンスや歌を披露する。最先端のCGに慣れきった観客は、どんなにすごい映像を観ても「でもこれCGで撮ったんでしょ」と冷めた目で見るようになってきているだけに、その躍動感は非常に新鮮に映る。また、「アメリカン・アイドル」の振付師マンディ・ムーアによるエモーショナルなダンス、ゴージャスさとセンチメンタルさが同居した音楽なども心に迫る。
美術や衣装も、赤、青、黄といった原色を使ったカラフルでポップな色合いとなっている。衣装デザイナーのメアリー・ゾフレスによると、主人公のエマ・ストーンとライアン・ゴズリングだけでも50回以上も衣装を取り換えているそうで、そんなカラフルな衣装を観るのも楽しみのひとつだ。
昨年の反省やトランプ政権が結果に影響?
先述したとおり、アカデミー賞作品賞は、すべてのアカデミー会員の投票によって決定される。つまりノミネートされた部門が多ければ多いほど、その作品を支持する会員の数が多くなるのは必然となる。ハリウッドが「夢の王国」だった時代を現代にもう一度よみがえらせたいという若き監督の野心に、アカデミー会員が共鳴した――、というシナリオで今回のアカデミー賞は進むと思われただけに、黒人の貧困、ドラッグ、LGBTといった現代のアメリカが抱える問題と真っ正面から向き合った『ムーンライト』の逆転受賞には驚かされるばかりだった。
なぜ『ラ・ラ・ランド』は作品賞を逃したのか。その理由はもちろん投票したアカデミー会員ひとりひとりに聞いてみないと分からないところだが、あえて理由を分析すると、「昨年の“白すぎるオスカー”批判の反省」「多様性を認めないトランプ政権に対するハリウッドからのメッセージ」といった部分もあったのかもしれない。アカデミー賞では時折、大本命と言われた作品が作品賞を逃すということがある。そこがアカデミー賞予想の難しさでもあり、面白いところでもある。
日本でも、2月24日、アカデミー賞発表直前というまたとないタイミングで初日を迎えた。全国で満席の劇場が続出しているが、エマ・ストーン演じるミア・ドーランの愛車がトヨタのプリウスだったりと、日本人の心をくすぐるシーンもいくつかちりばめられているのも見どころだ。
作品賞は逃したものの、早くも「今年のベスト!」と興奮した声もあがる。興行収入50億円超の大ヒットも夢ではないかもしれない。
【構造・衣装・心情】『ラ・ラ・ランド』が私たちに見せてくれた、夢
古き良きハリウッド感ミーツ現代
それは、登場人物が着ている色とりどりのドレス等のファッション、街並を飾るポスター、なにより今作におけるキーワード「ジャズ」が我々に50年代を感じさせる要素となっているからなのです。
50年代のファッションといえば、カラフルでカラーブロック。そしてジャズにとっては“黄金時代”とも呼ばれていた時です。ジャズピアニストであるセバスチャン(ライアン・ゴズリング)も、ケニー・クラークやマイルス・デイビスの崇拝者であり劇中に何度も彼の名前やジャズについて語っている事から、現代と50年代のリンクがより一層感じられます。
また、ミアがお気に入りのスタジオをセバスチャンと見てまわる際に見えるセットも、現代のCGIを多用する映画とは違い、明らかにペンキを手塗りしたようなもので、全てを手作りで作っていた時代のハリウッドを思わせますよね。この未来への希望と期待に満ち溢れた映画全体の“古き良きハリウッド感”が、現代のエネルギーに交わっている。そのミスマッチが面白いんです。
この新古の交わりは、今作において最も重要である音楽でも表現されています。
セバスチャンは古き良きジャズミュージックのファンであり、それに憧れるジャズピアニスト。彼はどうにかして、またこの現代にジャズを復活させたいと思っています。さて、彼が友人(キース/ジョン・レジェンド)のバンドに向かい入れてもらった時に初めて行ったジャズ調のセッションで、友人がMIDIパッドを使用するシーンがあります。これぞまさに、従来の音楽ミーツ現代サウンド。
セバスチャンはこれを「ありえない」と不機嫌に捉えますが、それに対し友人は逆に「お前のそういうところがめんどくさい、お前のようなやつがジャズを殺すんだ。過去にとらわれすぎている」という風に言い返します。
このやりとりは「あの頃は良かった……」と文句を言うだけの、現代に生きる懐古主義者に対して、この映画が「受け入れた上で前に進め」と革新していく事の重要性を伝えているようにも感じます。
ショットの構造から読み解く心情
ミュージカルであり、ドラマであり、ロマンス映画である今作はとにもかくにも技術も高く、魅力的なショットが多いです。そして、ロマンス映画において最も重要と言っても過言でないのが、登場人物の心情描写。
ここからは、ショットの構造からミアとセバスチャンの心情を探っていきたいと思います。
「A Lovely Night」が終わった直後のシーンで、セバスチャンはひとり自分の車に戻ります。
車に乗った時、カメラは助手席の奥から運転席に座るセバスチャンを捉えている。このぽっかりと空いた奥行きが、今まで誰か(ミア)と一緒にいたのに、別れて一人になって感じる空虚感を描いています。
そしてもう一つ注目したいのは、ミアが素晴らしい「Audition」を披露した後、「A Lovely Night」で共に踊った思い出の丘のベンチにセバスチャンと座ってこれからの事を話しているシークエンス。
将来の事を話し、オーディションの結果は出ていないのに、お互いがこれから物理的に大きく距離が離れる予感を察知しています。恋仲である以上に、お互いの将来を支え合ってきた二人は、改めて自身の夢に対して向き合うのです。
ミアが「初めてお昼にここにきたわ」と言って、二人して「最低な眺めだ」と笑いながら思い出の展望台を見上げる。この時、展望台を含めた周りの景色がミアとセバスチャンより圧倒的にスペースを占めていて、彼らは豆粒のような小ささで映っています。このショットから、これからお互いが向かう世界があまりにも大きく、彼らがちっぽけな存在であるという自覚と不安、そして期待を抱いている心情が読み取れます。
カラフルな衣装が意味するもの
今作の衣装を手がけたのは、これまでに数多くの名作でその才能を発揮してきたベテランの衣装デザイナーであるメアリー・ゾブレフ。
赤、青、黄色とヴィヴィッドで華やかな衣装は、ただ綺麗なだけではなくてその色にも心情などを表す意味を秘めているのです。
注目したいのは、ミアとセスの服のカラーの変化。
ミアは映画冒頭からブルーやカナリアイエローのドレスなど、基本的にカラフルな服を着ています。これは、彼女の周りに対して非常にオープンで快活だという人柄を表しているのです。
逆に、セスが着ていた服を思い出してください。ミアと再会を果たしたパーティで、彼が着ていたのは黒のタキシードに黒のタイ(演奏中は違いますよ)。周囲は男性でさえパープルのジャケットなど、黒い服を着ていない。劇中黒のタキシードを着ていた男性はいたものの、タイはカラフルなのです。
それなのに彼だけが黒という何にも染まらない色を着ていたのは、「自分はプロで、こんなパーティで軽く弾くようなアーティストではない。ここにいるべき人間ではないんだ」という周りに対する決別での意思、その空間に交わっていない事を意味しているように感じます。
しかし、ミアとダンスをして彼女に惹かれた彼が職場のカフェまで行ってデートに誘ったあの日から、彼は基本的にベージュやブラウンのセットアップを着るようになりました。
ベージュは何にでも合う包括的な色であり、それは彼が周りに対して(特にミアに対して)心を開いて交われるようになったという変化を表しています。
彼がバンドミュージシャンとして活動している時は、やはりあの黒のタキシード。彼にとっての本当の居場所は、ステージの上でもなくて、やはりミアの隣だということがわかりますね。
一方でミアにも服のカラーに変化があります。
基本的にいつもカラフルだったミアが、ラストシーンで旦那とセバスチャンの店にやってくる時、初めてブラックドレスを着ていました。そして席につき、舞台にいるセバスチャンと目が合う。
彼の着るブラウンのセットアップは、彼が従来の卑屈さを克服し、ミアなしでも人に心を開けるようになったことを象徴しています。一方、ブラックドレスを着るミアは、今の夫が自分にとって本当にしっくりくる相手ではないという事、本当の居場所は客席ではなくセスの横だという意味で、先述のセバスチャンと同じ心情で周りから孤立しているのです。
全収録曲レビュー:夢と情熱の旋律
ジャスティンも、同曲の作曲は「大変だった」と振り返っている。幾度となく続いた書き直しは、「コーラスを入れられるようになった頃には、すっかり心が折れていた」と言うほど。ちなみにその印象的なメロディがジャスティンに”降りてきた”のは、ヴェネツィアにてデイミアン・チャゼル監督と同じ部屋で作業をしていた時のこと。デイミアンが脚本を執筆し、ジャスティンが何となくピアノをいじっていた時にメロディが浮かび、デイミアンも気に入ったのだという。
Someone In The Crowd (Emma Stone, Callie Hernandez, Sonoya Mizuno, Jessica Rothe)

報われない日々に辟易としていたミアを、ルームメイトの友人がパーティーに連れ出すシークエンスで華やかに歌い上げられるのがこの「Someone in the Crowd」だ。マリウスは「この曲も複雑だった」と振り返る。
アパート内から路地へ、 そしてパーティー会場、プール、最後には花火も上がる同曲シークエンスは、「色々なピースが、色々なタイミング、色々な場所で展開されるので、製作には何年も費やした」とジャスティン。別の場でも「この映画の中で一番ヤバい撮影だった」と振り返っているから、相当な労力を要したようだ。映画ではカラフルなジェットコースターのような見事な映像となったが、バラバラに撮影されたショットが上手く繋がった映像を見て、マリウスもホッとしたという。ちなみに撮影に至るまでの楽曲制作にも苦労があり、一度は気に入っていた歌詞を2014年時点ですべて放棄し、ジャスティンはまた新たな歌詞で作曲に打ち込んでいる。
マリウスによればこの曲は「編集段階で変更が生じた、珍しい曲」なのだという。「当初は”2番”があって、もう少し演出と振り付けがあったんです」と言うことは、幻の2番があるということか。なお、カットされた理由は、「ここではもっと物語を進めておくべき」との判断のため。ジャスティンはもう少し詳細を語っていて、「観客がミアの感情の起伏を見失うようだったから。ルームメイトたちを長く追いすぎていたので、カットしたんです」とのこと。
ジャズ・バーの演奏にアーティスト性を込めたいセバスチャンと、ツイてない出来事が連続して気の落ちているミアが出会うシーン。繊細な表情をしながらも、行き場のない感情が絡みつくようなピアノ演奏を聴くことが出来る。
「ここで大事なのはライアン(・ゴズリング)。彼のピアニストとしての旅路の下積み時代です」とマリウス。ライアン・ゴズリングは今作のため実際にピアノをイチから練習しており、映画で観られる演奏シーンは手元のアップまで全て差し替え無しだ。
このシーンの撮影は本作の中でも初期に行われており、マリウスはその撮影時のエピソードを共有している。
「皆ちょっと緊張していました。でもライアンの1テイク目が終わると、拍手が巻き起こるまで少なくとも10秒は皆驚いてシーンとしていましたね。」
プールパーティーで再会したミアとセバスチャンは、2人で互いの車のもとまで戻る。マジックアワーの夕空に包まれながら、歌とタップダンスに乗せた2人の心は触れ合う手前まで接近する。
ジャスティンによれば、同曲はメインテーマよりも早く、最初期に作られた曲だそう。作曲が初められたのは2011年のこと。マリウスからは、もともと完成版とは全く異なる歌詞で準備が進められていたことが語られている。その内容は「ウィットに富んだ、クレバーな」ものだったというが、ライアンとエマの2人がキャラクターのトーンに合わないと感じたため書き直しに。作詞のベンジーとジャスティン・ポールが「繊細で、落ち着いた、穏やかに浮ついた、自惚れたような」歌詞を書き上げた。「それがあのシーンと楽曲に完全にハマってくれました」とマリウス。その内容についてジャスティンは、「絶対ありえないから、と言い合うものです。付き合うなんてありえないし、どうとも思ってないって。でも同時に、お互いに興味を持っている様子が見られます。恋に落ちているところなんですよね」と語る。
“スターの街よ、その輝きは俺のため?” ライトハウス・カフェでジャズへの理想論を語ったセバスチャンは、どうやら夢に向かって着実に歩んでいる様子のミアと別れた後、ひとり桟橋で黄昏るように歌う。”素敵な恋の始まりなのか あるいはこれも また叶わない夢なのか…”
セバスチャンは口笛を吹くが、実はライアン・ゴズリングは口笛が吹けないそう。代わりにこの場面では、ジャスティンの口笛に差し替えている。
ちなみにこのシーンの撮影時、美しいマジックアワーに包まれた水平線に、かなり大きな米軍戦艦が写り込んでしまっていた。後にプロデューサーのマーク・プラットが「10分ほどで消してくれた」とはマリウス談。
ボーイフレンドやその仲間とのディナーに同席したミア。それまでBGM程度にしか認識していなかったジャズに、かつてない愛着を覚える。セバスチャンへの想いを確信したミアは店を飛び出し、彼の待つ映画館へ向かう。2人は『理由なき反抗』(1955)を上映する映画館から、グリフィス天文台へと移動する。
「『Planetarium』の始まり、2人が振り子の側でワルツを踊るところでは、演奏が気まぐれなんです」とジャスティン。そわそわするような2人の関係性を表現しているのだ。「フルートは震えていて、ピッチパーカッションとソロの木管楽器が互いに対話しているんです。」
演奏は、2人の距離感に呼応して盛り上がっていく。溢れ出すような頂点に達するのが、互いへの想いをついに抑えきれなくなった2人が、プラネタリウムが映し出す満天の星空の中にふわりと浮かぶ瞬間だ。ジャスティンはこの部分のスコアを解説する。
「舞い上がる瞬間は壮大にしたかったので、ティンパニ・ロールをアップビートで少し入れて、それから弦楽器隊の全部が各々のテクスチャーを持って入ってくるようにしました。それぞれがメロディの上にありながら、それぞれの旋律が調和し合っているんです。それから木管楽器が敷かれて、とは言っても互いが対位旋律になっています。」
「Planetarium」に大きな影響を与えた作曲に、フランスの生ける伝説ミシェル・ルグランによる傑作「シェルブールの雨傘」がある。最も、マリウスは「ジャスティンがたどり着いた優雅で洗練されたオーケストラ演奏は、他の(正当な)褒め言葉の中でちょっと見過ごされがちだと思う」と述べている。
夏の始まり、恋の始まりだ!デートを始めるようになったミアとセバスチャンの幸せの日々を、楽しく爽やかに彩る「Summer Montage/Madeline」。「この曲がミアとセバスチャンの関係の絶頂期だ」とマリウスも認める。確かに、2人にはこの後ほろ苦いすれ違いが続くこととなる。
実はこの曲、当初はコーラス隊を使いながら、ミアとセバスチャンのデュエットを聴かせる運びだったという。その名も「La La Land」とのタイトルまで付けられており、他のメイン曲と同じくらい長い時間を費やしていた。「だから、手放す時は少し辛かったですね。映画の流れがこの曲の重さを支えきれないと分かってしまったんです」とマリウス。
偶然再会したかつての仲間キースのバンドに加入することになったセバスチャンだが、保守派のセバスチャンはバンドの方針に心から納得できない。2人の生活のためには金を稼がなければならないことも分かり始めていたセバスチャンの前に、現実が顔を出す。それでも、今のセバスチャンにはミアという安らぎがあった。”スターの街よ その輝きは俺のため?”ピアノの弾き語りを始めたセバスチャンのもとに、ミアが寄り添って歌う。
2人のボーカルはライブ・オンセット、つまり別撮りでなく撮影時に歌われたもの。劇中唯一、弾き語りに挑んだライアンにもご注目。
セバスチャンが加入したキースのバンド「ザ・メッセンジャーズ」で華々しく演奏された「Start a Fire」を、マリウスは「これはジャズの純性と先進性のせめぎ合いを表したデイミアンのニュアンス表現によるものです」と解説する。「それが、ミアとセバスチャンの深刻な関係性の明示になっていく。」
キースを演じ、このシーンで魅力的な歌声を聴かせているのは有名歌手のジョン・レジェンド。「オーディナリー・ピープル」など多くの名曲で知られ、グラミー賞10冠に輝く超実力派シンガーだ。『ラ・ラ・ランド』は映画初出演となった。
デイミアンがジョンにオファーを出した頃、まだジョンを出演者として迎え入れるか、楽曲提供のみとするか決めかねていた。一方ジョンは、ミュージシャンを描いた監督の前作『セッション』(2014)を観て「彼ならうまくやってくれそう」と感じていたという。ちなみに、同作でピアノからタップダンスまで習得したライアン・ゴズリングの才能には「実はちょっと嫉妬しました」と語っている。
エレクトロ・サウンドなど現代的なアプローチをふんだんに取り入れた「Start a Fire」のライブでは、ダンサーまで登場する派手な演出でフロアを湧かせた。セバスチャンのプレイを見に来ていたミアも、始めこそ華やかなステージングを喜んだが、セバスチャンの思想とはあまりにもかけ離れたバンドの創造性に戸惑う。
ジョンが語るには、デイミアン監督が同曲に求めたのは「実際にいい曲であり、普通に聴けて、楽しいもの。でもセバスチャンがやりたい方向性とは明らかに違うもの。そのバランスを狙っていました。」
「革命を起こすなら、伝統に固執するな。過去にしがみつくなよ。ジャズは未来だ。」──革新派のキースは、ジャズに対する価値観がセバスチャンとは真逆。「お前はケニー・クラークやセロニアス・モンクにこだわるが、彼らだって革命家だっただろ。」ミュージシャンであるジョン・レジェンドには、キースの考えが分かるという。
「キースの言っていることには同意です。音楽やあらゆる芸術における”偉人”は、過去の真似事ではなく、その芸術で革命的なことをやってきました。過去に影響されたり歴史にヒーローを見出すことも重要ですが、前進して新しい何かを創り出すことも、同じくらい重要。成功したアーティストは皆、どれだけ他のアーティストから影響を受けていようが、革新的なことをやっているものです。」
やがて2人は、互いの間に決定的な「価値観の違い」が存在することに気付いてしまう。セバスチャンは仕事の予定を失念しており、ミア初の独演舞台に行きそびれる。駆けつけた頃には既に終演しており、ミアにとっても舞台は失敗に終わった。全てに限界を感じたミアは実家に帰ることを決意。再びセバスチャンは独り身となり、ミアは実家の自室で夢破れたことを思い知る。
「Engagement Party」は、セバスチャンがピアニスト役を務めた結婚式のパーティで演奏される。幸せそうな新郎新婦と自身の境遇のギャップにやるせなさを感じさせる曲だ。「運命の誰かに出会えるかも」と歌った「Someone in the Crowd」のスローアレンジになっている点も切ない。マリウスは、「(「Someone in the Crowd」にあった)豪華なパーティーのエネルギーを、この穏やかで切なく、鬱な形に変化させたのが愛おしい」と語っている。
ミアの夢は潰えていなかった。独演舞台を観た関係者が、オーディションの場を設けたいとセバスチャンに連絡していたのだ。セバスチャンは彼女をロサンゼルスに連れ戻す。
これまでオーディションでさんざんな目に遭ってきたミアはこの日も気乗りしない様子だったが、最初に映画の具体的な企画内容を聞かされた彼女の目に「チャンスかも知れない」という反応が見られる。オーディション内容は自由演技。ミアは叔母の物語を語り始める…。
ジャスティンにとっては、「おそらく今作の中で一番好きな曲です」と語るほどのお気に入り。どうやら、閃きに恵まれた作曲プロセスのためでもあるようだ。
「たとえば、他の曲ではインスパイアを得るためにフレッドとジンジャー(※)の曲や色々な参考曲を聴いたのですが、『Auditon』の時は何も聴きませんでした。何にも似せようとしませんでした。ただピアノで作曲したんです。だから、非常にピュアな形で生まれた、感情が作り上げた曲のように思います。ピアノの前に座って、この曲はどうなるのかな、歌詞が入ったらどういう曲になるのかな、と考えていたのはとても良い経験になりました。」
ジャスティンに曲が降りてきてから完成までは早く、書き直しは微調整程度だった。重要なのは撮影だ。「あの曲を彼女と準備して、撮影に挑むまでは長かったです」とジャスティンが語る一方で、マリウスは次のように述懐する。
「エマにとっては間違いなく大事な場面でした。現場の彼女に対し、私達は皆不安でした。エマ1人の撮影ですし、クローズアップも多く、メロディも高低あって難しい。ストーリーの中でも非常にエモーショナルな部分です。それに、ボーカルも現場で録音されるのですから。」
そんな心配は杞憂だったことは、本編をご覧になれば分かる通り。マリウスは「彼女は大健闘でした」と、ジャスティンも「素晴らしい仕事をしてくれた」と語る。「映画の中で聴けるのは、すべて彼女のライブ歌唱なんですよ。」
撮影時、エマは小型のイヤフォンを装着し、別室でジャスティンが弾く電子キーボードに合わせて歌った。「彼女はリハーサルでモノにしてくれました。」エマは撮影日までに猛練習を積み、仕上がった状態だった。ジャスティンは「彼女が曲をリードしてくれて、私はただ同伴しただけでした」と語る。「全テイクがこれまでにない経験でした。撮影時の形式であの曲を演奏したことがなかったからです。現場の全員が感動しきりで(エマの演技を)見ていましたね。」
「Audition」の歌詞は、ミアが女優を目指すきっかけとなった叔母の昔話。冷たいセーヌ川に飛び込んで、風邪を引いてもまた飛び込むという叔母に、夢追い人の姿を重ねたものだ。ジャスティンは、「このメッセージは明白で、飛び込む価値はある、ということ」と解説する。
「この曲のテーマは、ミアとセバスチャンの関係にピッタリと結びついています。それから愛と喪失を経験した私達にもね。恋をして、燃え尽きて、痛む心を抱えなければならないこともあるかもしれません。それでも、試す価値はある。彼女の歌詞は最後にこう言います。”笑って跳んだ。おばは言った、もう一度跳ぶと──”」
5年後の冬。2人は、思い描いていた未来とは違う道を歩んでいた。オーディションに合格したミアは、今やハリウッド女優として成功していた。ハンサムで優しい夫デイビッドと結婚し、子宝にも恵まれた。一方セバスチャンは、念願のジャズ・バーを開業。大好きなジャズをたっぷり演奏できる日々を過ごしていた。
そのジャズ・バー「SEB’s」に、ミアは夫と偶然入店(いや、運命と言うべきか)。ミアは、今や人気店のオーナーとなったセバスチャンを見上げ、セバスチャンも客席にミアを見つける。別れる前、「ずっと愛している」と交わしたはずの2人に「あり得たかもしれない現実」とは──。マリウスが語る。
「信じられないほど大胆なシークエンスで、『ラ・ラ・ランド』における感情表現がいかに複雑であるかをよく表しています。後悔、記憶、受け入れ。そのダンスが、豊かな映像によるストーリーテリングと結びつく。哀愁とユーモア、無邪気さと喜びが創造的なプロセスの中で全てひとつになって踊り、ラストへ向かっていく。ミアとセバスチャンの間の、名残惜しい視線です。」
なおラストシーンには、ジャスティンが自宅のピアノで演奏していたものを離れたマイクで録音した音源が使われている。「デモのつもりだったのですが、その儚い響きをデイミアンが気に入ったんです。スタジオでしっかりレコーディングしたものではありません。でも、求めていた感情が表現できていたので使ったんですよ」と語るのは、幻想が現実に重なる場面で儚く聴こえる、涙のようなピアノの単音演奏だ。
あり得たかもしれない現実。何かが、どこかで違っていれば、ミアとセバスチャンは今も一緒にいたのかもしれない。当たり前のように手を繋いで、何気ないジャス・バーに立ち寄っていたのかもしれない。
City of Stars (Humming) (Justin Hurwitz featuring Emma Stone)

シティ・オブ・スターズ(ハミング) – ジャスティン・ハーウィッツ feat. エマ・ストーン
サウンドトラックが映画体験を深める理由
『ラ・ラ・ランド』のサウンドトラックは、単なる映画のBGMではありません。それぞれの楽曲が、登場人物の感情、物語の展開、そして映画全体のテーマと深く結びついています。歌詞のある曲では、登場人物の心情が সরাসরি 表現され、インストゥルメンタルでは、言葉にならない感情や情景が豊かに描き出されます。
特に「Mia & Sebastian’s Theme」は、映画全体を通して様々なアレンジで登場し、二人の関係性の変化や感情の機微を象徴的に表現しています。また、「City of Stars」は、希望と葛藤が入り混じる夢追い人の心情を代弁し、多くの観客の共感を呼びました。
ジャスティン・ハーウィッツの音楽は、ジャズ、ミュージカル、ポップスなど、様々なジャンルの要素を取り入れながらも、一貫した美しい旋律とハーモニーで構成されています。その音楽は、映画の映像と一体となり、観る者の感情を揺さぶり、物語の世界へと深く引き込みます。
『ラ・ラランド』登場人物と出演者たち
ライアン・ゴズリング(セバスチャン・セブ・ワイルダー役)

『ラ・ラ・ランド』の主人公のひとり、ジャズに焦がれ、同時にその行く末を憂いながらも自身の店を構えたいと夢見るピアニストのセブを演じるのは、いまや映画ファンには説明不要の人気俳優ライアン・ゴズリングだ。
1980年生まれ、1993年から子役としてキャリアをスタートさせたライアンが大きな注目を浴びたのは、レイチェル・マクアダムス共演の恋愛映画『きみに読む物語』(2004)。その後は『ハーフネルソン』(2006)や『ラースと、その彼女』(2007)、『ブルーバレンタイン』(2010)などで高い評価を獲得。『ドライヴ』(2011)や『オンリー・ゴッド』(2013)などのスリラー/犯罪映画にも数多く出演した。
キャリアを通じて、ライアンはロマンティック・コメディからダークなSFドラマまで作品の規模やジャンルを問わず実力を発揮。近年は『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(2015)や『ナイスガイズ!』(2016)、『ブレードランナー 2049』(2017)などに出演した。2014年には監督デビュー作『ロスト・リバー』(2014)を発表、第2作を準備中とも報じられている。最新作は『ラ・ラ・ランド』デイミアン・チャゼル監督と再びタッグを組んだ『ファースト・マン』(2019年2月8日公開)。
エマ・ストーン(ミア・ドーラン役

『ラ・ラ・ランド』もうひとりの主人公は、いつかスター女優になることを夢見ながら撮影所のカフェで働くミア。演じるエマ・ストーンは1988年生まれで、2004年にテレビドラマで活動を開始した。
エマの映画デビュー作は、青春コメディの傑作として愛される『スーパーバッド 童貞ボーイズ』(2007)。その後も『ゾンビランド』(2009)や『小悪魔はなぜモテる?!』(2010)などコメディ映画を中心に活躍したエマにとって、大きな転機は『アメイジング・スパイダーマン』(2012)への出演だった。エマは知名度を大きく伸ばし、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(2014)で多くの映画賞にノミネート。『ラ・ラ・ランド』ではアカデミー賞主演女優賞などを射止め、『バトル・オブ・ザ・セクシーズ』(2017)の演技も高く評価された。
近作には久々のドラマ出演となった「マニアック」(2018)があるほか、『女王陛下のお気に入り』(2019年2月15日公開)ではアカデミー賞助演女優賞へのノミネートされた。いまやオスカー常連となった感もあるが、次回作は10年前に出演したゾンビ・コメディの続編『ゾンビランド:ダブルタップ(原題:Zombieland: Double Tap)』。作品の選び方も厚い支持の理由かも…?
ライアン・ゴズリングとエマ・ストーン

『ラ・ラ・ランド』に欠かせない組み合わせであるライアン・ゴズリング&エマ・ストーンは、実は本作が3度目の共演となる。1度目はロマンティック・コメディ映画『ラブ・アゲイン』(2011)で、2度目は犯罪映画『L.A. ギャング ストーリー』(2013)だ。
それぞれ異なるジャンルながらも『ラ・ラ・ランド』を含めて共通するのは、すべての作品で二人は恋愛やそれ以前の関係性を演じ、それぞれに酸いも甘いも演じ分けてきたところ。二人にとってミュージカル映画は新境地となったが、“歌わない”シーンの繊細さと切実さもまた本作の白眉。ライアン&エマによる演技の妙をじっくりと堪能してほしい。
ジョン・レジェンド(キース役)

セブの旧友にして物語のキーパーソンであるキースを演じるのは、人気・実力ともにトップのR&Bアーティスト、ジョン・レジェンドだ。1978年生まれのジョンは2000年に活動を開始し、2006年のグラミー賞で最優秀新人賞と最優秀R&Bアルバム賞、最優秀男性R&Bボーカル・パフォーマンス賞を受賞、その他5部門にもノミネートされている。その後、ジョンは2007年・2009年・2011年・2016年にもグラミー賞に輝いてきた。最新アルバムは2018年10月にリリースされた「A Legendary Christmas」。
ジョンは歌手活動だけでなく俳優業にも積極的に挑んでおり、『ラ・ラ・ランド』以外にも『ソウルメン』(2008)やドラマ「マスター・オブ・ゼロ」シーズン2(2017)に出演、ロックオペラ「ジーザス・クライスト=スーパースター ライブ・イン・コンサート」(2018)では主演・製作を兼任して高い評価を受けた。なお『グローリー/明日への行進』(2014)には、人気ラッパーのコモンとコラボレーションした主題歌「Glory」を提供し、アカデミー賞・ゴールデングローブ賞にて主題歌賞を受賞している。
J・K・シモンズ(ビル役)

セブが働くレストランのオーナーとして登場するのは、デイミアン・チャゼル監督の前作『セッション』(2014)でキャリア屈指の迫力をもって鬼コーチを演じたJ・K・シモンズ。短い出番ながら、本作でも確かな存在感を発揮している。
1955年生まれのシモンズは1986年から俳優としてのキャリアをスタートさせ、ドラマ「ロー&オーダー」(1994-2010)のエミール・スコダ博士役で知られる。映画ではサム・ライミ監督による『スパイダーマン』3部作で人気キャラクターのJ・ジョナ・ジェイムソンを演じたほか、『JUNO/ジュノ』(2007)や『ターミネーター:新起動/ジェニシス』(2015)、『ザ・コンサルタント』(2016)、『ジャスティス・リーグ』(2017)などに出演した。近作にはヒュー・ジャックマン主演『フロントランナー』(2018)、主演ドラマ「カウンターパート/暗躍する分身」(2017-、WOWOWで2019年2月より日本放送)などがある。
ソノヤ・ミズノ、ジェシカ・ロース、キャリー・フェルナンデス(ルームメイトたち)
最後にご紹介したいのは、エマ・ストーン演じるミアのルームメイトを演じている3人の女優だ。驚くべきことに――『ラ・ラ・ランド』本編にも通じるように思われるが――いまや3人とも映画界で未来を期待される注目の新鋭となりつつある。
映画前半に登場する「Someone in the Crowd」のシーンで黄色いドレスに身を包んでいるケイトリン役を演じているのは、日系人女優のソノヤ・ミズノ。東京生まれのイギリス育ちで、父親は日本人、母親はイギリスとアルゼンチンのハーフだという。
ソノヤは『ラ・ラ・ランド』以前に『エクス・マキナ』(2014)に出演しているほか、実写映画版『美女と野獣』(2017)やNetflixオリジナル映画『アナイアレイション -全滅領域-』(2018)、米国で大ヒットとなった『クレイジー・リッチ!』(2018)といった話題作に出演。エマ・ストーンとはドラマ「マニアック」でも共演している。次回作は『エクス・マキナ』『アナイアレイション -全滅領域-』のアレックス・ガーランド監督が脚本・監督・製作を務めるドラマ「Devs(原題)」で、なんと主演に抜擢された。
緑のドレスを着ているアレクシス役を演じたジェシカ・ロースは、『ラ・ラ・ランド』以降、今まさにキャリアを飛躍させようとしている新鋭だ。ダコタ・ファニング主演『500ページの夢の束』(2017)や主演映画『Forever My Girl(原題)』(2018)のほか、注目すべきは全米で大ヒットしたホラー映画『ハッピー・デス・デイ(邦題未定、原題: Happy Death Day)』(2017)、続編『ハッピー・デス・デイ・トゥー・ユー(邦題未定、原題:Happy Death Day 2U)』(2019)に出演したこと。自分が殺される運命を変えるまで同じ一日を繰り返すという地獄のタイムループ・ホラーで人気を獲得し、さらなる活躍が期待されている。
そして、赤いドレス姿のトレイシー役を演じているのはキャリー・フェルナンデス。『ラ・ラ・ランド』以外には『ブレア・ウィッチ』(2016)で準主役を務め、各国の映画祭で話題を呼んだSFスリラー『アルカディア』(2017)でも主要人物のひとりを演じた。また『エイリアン:コヴェナント』(2017)にも出演したほか、アンドリュー・ガーフィールド主演『アンダー・ザ・シルバーレイク』(2018)には主人公の追う謎のカギを握っているキーパーソン役で登場している。
解説・あらすじ
「セッション」で一躍注目を集めたデイミアン・チャゼル監督が、ライアン・ゴズリング&エマ・ストーン主演で描いたミュージカル映画。売れない女優とジャズピアニストの恋を、往年の名作ミュージカル映画を彷彿させるゴージャスでロマンチックな歌とダンスで描く。オーディションに落ちて意気消沈していた女優志望のミアは、ピアノの音色に誘われて入ったジャズバーで、ピアニストのセバスチャンと最悪な出会いをする。そして後日、ミアは、あるパーティ会場のプールサイドで不機嫌そうに80年代ポップスを演奏するセバスチャンと再会。初めての会話でぶつかりあう2人だったが、互いの才能と夢に惹かれ合ううちに恋に落ちていく。「セッション」でアカデミー助演男優賞を受賞したJ・K・シモンズも出演。第73回ベネチア国際映画祭でエマ・ストーンが最優秀女優賞、第74回ゴールデングローブ賞では作品賞(ミュージカル/コメディ部門)ほか同賞の映画部門で史上最多の7部門を制した。第89回アカデミー賞では史上最多タイとなる14ノミネートを受け、チャゼル監督が史上最年少で監督賞を受賞したほか、エマ・ストーンの主演女優賞など計6部門でオスカー像を獲得した。
まとめ
『ラ・ラ・ランド [オリジナル・サウンドトラック]』は、映画の感動を再び味わうことができるだけでなく、音楽作品としても非常に完成度の高い一枚です。夢を追いかけるエネルギー、恋の喜びと切なさ、そして人生の選択といった普遍的なテーマが、美しいメロディーと心に響く歌詞によって鮮やかに描き出されています。
映画をまだ観ていないという方も、このサウンドトラックを聴けば、きっとその魅力に引き込まれるはずです。日常に彩りを与え、心を豊かにしてくれる『ラ・ラ・ランド』の音楽を、ぜひあなたの生活に取り入れてみてください。このサウンドトラックは、きっとあなたの心にいつまでも残る、特別な一枚となるでしょう。













![ラ・ラ・ランド [オリジナル・サウンドトラック]](https://muutos-p.net/wp-content/uploads/2025/05/shikun-_R5A3503-01-12903_TP_V4-1.jpg)